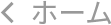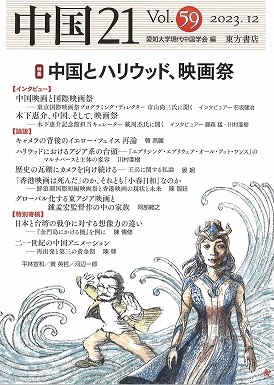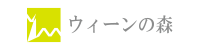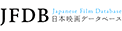東京国際映画祭公式インタビュー:
アジアの未来
『マリア』
エルナズ・エバドラヒ(プロデューサー/編集)、カミャブ・ゲランマイェー(俳優)

映画監督のファルハドの結婚式当日。彼が運転する乗用車に突然落下した若い女性が激突し、車は大破する。陸橋から落ちたその女性・マリアは意識不明の重体。ファルハドは彼女の家族に会い、なぜ彼女が陸橋から落ちるに至ったのかを聞くものの、どうにも歯切れが悪い。事故、自殺未遂、事件、どの可能性も捨てきれない胡散臭さが漂うなか、マリアはファルハドが2年前に撮影したある映画に出演していたことがわかる……。
ネット流出画像・動画による暴力の可能性、民族・宗教的な慣習による偏見と差別。映画業界の裏側を舞台に、これらに切り込みつつも、謎解きミステリーのような構成でみせた『マリア』。テレビ業界で監督として活躍し、テヘランの映画演劇スクールの講師を務めているメヘディ・アスガリ・アズガディの長編デビュー作だ。彼のパートナーであり、本作の編集・プロデュースを担当したエルナズ・エバドラヒと、これが映画デビューとなるファルハド役のカミャブ・ゲランマイェーに、プロダクションの裏側を聞いた。
――素晴らしいデビュー作でした。監督が来日できなかったのは残念です。
エルナズ・エバドラヒ(以下、エバドラヒ):夫(監督)にとっても日本は初めてでしたし、一緒に来たがっていたんですが、兵役の都合でどうしても無理でした。
――この作品は実話がベースと作中で何度かスーパーが出ます。とんでもないストーリーですが、実際はどういった事件だったんでしょう。
エバドラヒ:監督はイラン東部にある第二の都市マシュハドの出身なんですが、そこで暮らしていたころに聞いた話がもとになっています。4~5年前に起きたという実際の事件はこんな感じです。どうしても役者になりたかった若い女性が、家族には内緒で映画に出演し、娼婦の役を演じました。それが家族にばれてしまい、家族は彼女を殺そうとしたほど激怒したそうです。そればかりか共演の俳優、スタッフ、カメラマンなども殺そうとした、と。
こういったタイプの事件は「家族の恥」になってしまうため、メディアでは大きく扱いません。地元でも人々の間では話題にはなったものの、ニュースメディアに載ることはなかったそうです。その当時の監督は、まだテヘラン大学時代。マシュハドからテヘランに引っ越しをしようとしていたころに事件が起きたので、いずれ映画にするために好奇心からさまざまなリサーチをしました。そのときのヒアリングデータをもとに脚本を書き上げたんです。

――ゲランマイェーさんはこの事件をご存知でしたか?
カミャブ・ゲランマイェー(以下、ゲランマイェー):監督とは友達なので、こういう話があったよとなんとなく聞いていました。脚本をいただいたときに監督から詳しく説明され、詳細がわかりました。

エバドラヒ:監督はアスガー・ファルハディ監督の『英雄の証明』(21)を観て、本作の構成のアイデアを得ています。事件が起きて、その映像がネットで流出してから色んなことが起きるという『英雄の証明』のような構成にして、あの事件を撮れるんじゃないかと考えつきました。
ちなみに『英雄の証明』は、実際の事件をドキュメンタリー“All Winners, All Losers”(19)にした女性監督(アザデ・マシザデ氏。アスガー・ファルハディ監督の元生徒)が公開後に「パクりだ!」といってブチ切れたんですよ(実際は事件当事者で主人公モデルになっている男性とともに告訴し、ファルハディ監督は名誉毀損で反訴した)。そのとき、ファルファディ監督は「現実は誰のものでもないんです」と語り、誰でもシェアできることを主張しました。このセリフはこの映画の中に入れています。
ゲランマイェー:そのセリフは、そのままそっくりでは使ってないのですけれども、私が演じたファルハドが妻のパリサにつめられたときに言っています。「いろんな映画監督が、現実に起きてる事件や人生からヒントをもらって脚本書いて映画を撮っている。僕だってそういうことしただけ」と説明しているシーンです。
エバドラヒ:じつはファルファドっていう名前、ファルハディの逆読みなんです。夫はファルハディ監督を尊敬してるので(笑)。
――実際の事件をどれくらい脚色しているんでしょう?
ゲランマイェー:だいたい7~8割は実際に聞いた話。できるだけ真実に近く書こうとしたそうです。脚色したのは舞台になる街と民族性ですね。若い女性をバローチ族ということにしているのはフィクションです。
――バローチ族というのはどういった特性を持っているんでしょう?
ゲランマイェー:バルーチ族は、何が起きても自分たちの間で継がれている伝統的な方法でなんとかしようとします。この事件は、家族の間で問題の中枢にいる女性ごと隠匿しようとしたことが特徴。だからマリアの一家の設定をバローチ族にしたんです。
――現実には全く違うんですね。
エバドラヒ:実際、事件が起きたのはマシュハドですが、そこはバローチ族とは全く関係ありません。それにマシュハドを舞台にするのではなく、テヘランを舞台にロケすることを決めていたので、移動する少数民族がぴったり。バローチ族はもともとの居住エリアに日照問題があり、多くの人がさまざまな街を移り住んでいるのです。
また、監督は伝統とモダンのコントラストをこの作品に入れたかったことも大きいですね。バローチ族は伝統的な慣習を持った人たちなので、家や服装など、テヘランの都会の文化とはかなり違った文化を持っています。彼らとテヘランの都会人の生活の対比をさせることで、コントラストを表現できる、と考えたんですね。
バローチ族に関してはたくさんリサーチしました。バローチ族出身のアドバイザーが全てを監修し、美術デザインや衣装、言葉遣い、あと悪魔祓いの儀式などの独特な慣習などを学びました。
ゲランマイェー:マリアの祖父はボス的な感じですよね。それも彼らの決まりです。また、女性が2年間監禁されてた理由も伝統のひとつ。バローチではない人もバローチの家に行って「助けてくれ、殺されるから守ってくれ」って言ったら、絶対守るんですって。
――キャスティングのプロセスは?
ゲランマイェー:僕は、監督が講師を努めている演劇学校で4年前学んでいました。このプロジェクトが動き始めたときに、学生の中でテストし、僕が幸い選ばれました。全く経験がなく、短編映画にも出てなかったので、監督はロケハン時に僕を連れて行ってくれて、そこで軽く写真や動画を撮って芝居の練習をしたりしました。
――ロケ先が多いですよね。ご苦労は?
エバドラヒ:ロケは23カ所あり、どこで撮るにしても許可が必要なのでかなり苦心しました。たとえば、女性が落ちる陸橋。あれは撤去が決まっていた陸橋なので、撤去される直前に撮影のスケジュールを組みました。また、砂利道の坂道を上がっていくシーンは、あるセメント工場の道なんですが、全く許可が降りなかったんですよ。でも、アッバス・キアロスタミ監督の作品のオマージュなので、どうしても入れたい。なので早朝、工場が始まる前に行ってパッと撮影して撤収しました。
――ゲランマイェーさんが初演技とは思えなかったです。
ゲランマイェー:鏡の前でいっぱい練習しましたよ(笑)。ファルハドは本当に難しい役でした。彼は自分が観ているものを映画のアイデアにしようと、いつも頭の中に強烈なイメージを持っているキャラクター。そのせいか、今もたまにイメージが出てきてしまい困ってます。というのも、僕も彼のように自分が見ているものを、「これが映画だったら」みたいに考えるくせがあったんですよ。この作品に出演したことで、そのくせがどんどん強くなってしまいました。

――東京では現実に戻れましたか?(笑)
ゲランマイェー:余計ひどくなりましたね(笑)。現場では、共演者の大ベテラン、サベル・アバールさん(ペイマン役)と、パンテア・パナヒハさん(ゾーレ役)がいてくれたおかげで、彼らからのアドバイスでコントロールすることができました。じつは最初は少し怖かったんですけれども、彼らは親身になって教えてくれたので、難しい芝居もできるようになったんじゃないかなと思っています。
エバドラヒ:東京に行ったら絶対にこれを伝えてほしいと、監督から言付けがありました。終盤、パリサが左の目から涙を流すシーンと、そのあと意識を戻したマリアがICUで右の目から涙を流すシーン。これは対になっていて、マリアとパリサは表裏一体だったことを表現しようと監督は考えていました。
ものすごくわかりにくいことだけど、細部にこだわった作品。ぜひ次の作品で、または作品は選ばれなくてもゲストとして呼んでいただきたいと申しておりました。
インタビュー/構成:よしひろまさみち(日本映画ペンクラブ)