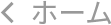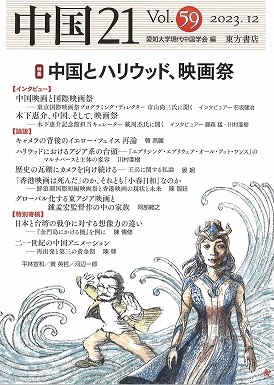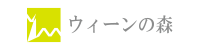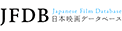東京国際映画祭公式インタビュー:
コンペティション
『エア』
アレクセイ・ゲルマン・ジュニア(監督/脚本)、エレーナ・オコプナヤ(美術/衣装)、エレーナ・リャドワ(俳優)

第二次世界大戦のレニングラード包囲戦に参加した、女性パイロットの軌跡をリアルに描いた作品。戦いに臨み、体験を重ねるうちにスキルを身につけるが、次第に心が空虚になる姿を写実的な映像とともに紡ぎだす。監督は『宇宙飛行士の医者』(08)や『ドヴラートフ レニングラードの作家たち』(18)で知られるアレクセイ・ゲルマン・ジュニア。年代記風に綴る迫真力に富んだ映像から、彼の戦争観が浮かび上がる。スケールの大きな仕上がりだ。
――作品を興味深く拝見しました。どういうかたちでプロジェクトが始まったのですか。
アレクセイ・ゲルマン・ジュニア(以下、ゲルマン監督):きっかけは、知り合いからの依頼です。ロシアでは実際、戦争についての映画がたくさん撮られていますが、ほとんどがブロックバスター大作です。私はそうしたくなかった。結果的に大作じゃない、静かな映画にしようと思い至りました。
美術と衣装担当のエレーナ(・オコプナヤ)は悩みました。時代を再現するのがかなり難しいからです。実際、時間はかかりました。何のためにこの映画が必要か、自分なりに理解するのは大事でした。自分はどんな気持ちでこの映画を撮るか、自分の考えを伝えるのが難しかったのです。

――もともと実話なのですか。
ゲルマン監督:実際に戦争に参加した女性のパイロットは数多くいました。戦闘機のパイロットもそうですし、爆撃機のパイロットも多かった。事実に基づいたというより、事実に触発されたストーリー。フィクションですね。事実に基づいたフィクションだと、自由に解釈ができます。実際、ソ連にも多くの女性パイロットがいて、例えばリディア・リトヴァクという人です。
――そのわりに、女性パイロットを主人公にした戦争映画は珍しい気がしますが。
ゲルマン監督:ソ連時代にも、戦う女性の有名な映画もありますし、今のロシア映画の中にも、女性ついての映画があります。実際、戦争時に女性は特に大変な状況に置かれていました。歓迎もされなかったし、もっと悲惨でした。現代のロシアの映画にも、第二次世界大戦の女性を描く映画がありますけれども、綺麗すぎて悲惨さと残酷さが伝わらないのです。
――監督の戦争に対する考え方がすごく反映されている映像だと思います。
ゲルマン監督:古典的な戦争大作にはしたくなかった。アメリカ映画でも、ロシア映画でも、戦争映画は美しい人たちが死ぬ時もとても美しい。でも戦争そのものは美しいものではありません。本当に悲惨、残酷で過酷なものです。死そのものも悲惨です。
私たちにはインターネットや携帯電話があって、世界の中の戦争の残酷さも分かっていると思います。自分の映画も事実に近い、リアルな見せ方にしたくて、フィクションだけどドキュメントリーのような見せ方を目指しました。ただ、ポエトリー(詩)の部分も残したかった。
――個性的な監督だと思いますが、一緒にお仕事をしているおふたりにとって、本作がどういう体験だったか教えていただけますか。
エレーナ・オコプナヤ:ドキュメンタリーのように本当にリアルに見せたかったので、自分のこだわりをお話しします。今、ロシアの戦争映画はトルコ製の生地を衣装のために使っています。綿ではなくてポリエステルなのです。当時、ポリエステルはなかった。こだわって、その時代の糸を作って衣装を作りました。
戦争で命を落とした人の状況に徹したかった。アレクセイ監督は古典的な映画を作る人です。私はそういう映画が好きです。今や、世界中の映画はストーリーを見せるだけ。綺麗に見せるだけでポエトリーとか個性が感じられません。今では予算が欲しければ、大ヒットさせなければいけないのです。私たちは監督とともに仕事ができて恵まれていると思います。

エレーナ・リャドワ:アレクセイ監督は、個性の強い監督で、今のロシアの中でも特別なスタイルのある監督だと思います。この映画はフィクションでもあり、ドキュメンタリー風に見せています。彼の他の映画を観ると、見せ方や個性がわかると思います。
アレクセイ監督の映画で演技をする時は、自分のキャラクターの気持ちや声を模索しなければならない。アキュラシー(正確さ)とかデリカシーも必要です。要するに、監督に合った演技をしないといけない。監督は印象派で、静かな映画であり、強い映画なのです。

――年代記風に女性パイロットの成長を描く展開を、最初から考えていたのですか。
ゲルマン監督:古典的な展開です。日本で言うと武士の道ですね。最初は若くて無垢ですが、成長して強くなる。でも死ぬのです。何度も脚本を書き、最初は登場する女性パイロットをみんな殺しました。5回目くらい書き直した時に、やっぱりひとりは生き残った方がいいと考え直しました。
ロシア人の反応と、日本人の反応と、他の国の理解は違うと思いますけれども、私が文化とか国にかかわらず伝えたかったのは“道”なのです。戦争は残酷にならなければいけない、強くならなければいけない。勇気を出さなければいけないと習って感情を失い、最後は死ぬ。蝶のような、短い人生にしたかった。
――これが取りも直さず、監督の戦争に対するものの考え方ですか?
ゲルマン監督:ソ連時代に生まれた私にとっては、戦争は身近でした。ソ連時代には、第二次世界大戦の死者は、統計的には2700万人ですが、実際は4000万人に近いといわれます。私の祖父も戦争で亡くなっています。戦争の歴史は心情の歴史、大事なのはその人たちの記憶と、戦争で身近な人を亡くした人に同情すること、亡くなった人を尊敬することです。
脚本を書いた時にはエレーナ・キセリョワさんがいて、互いに話したり、戦争についての小説を読んだり、あと音楽も聞いたりしました。なかでもブラート・オクジャワという、ロシアの詩人で歌手の歌に惹かれました。
――『宇宙飛行士の医者』は私の好きな映画だったんですけれども。やはりお父さんの影響で映画監督になったのでしょうか。
ゲルマン監督:それも要素のひとつです。

インタビュー/構成:稲田隆紀(日本映画ペンクラブ)