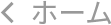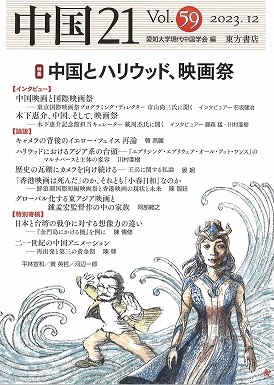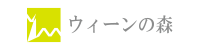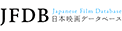東京国際映画祭公式インタビュー:
コンペティション
『ペルシアン・バージョン』
マリアム・ケシャヴァルズ(監督/脚本/プロデューサー)

アメリカに招かれたイラン人医師家族が、1979年のイスラム革命によって定住を余儀なくされる。ブルックリンで生まれた娘がアメリカの常識のなかで母、祖母をみつめ、自分も母となることで初めて理解する。マリアム・ケシャヴァルズが3世代に渡るイラン系アメリカ人女性像に迫ったコメディ。弾けたダンスシーンも織り込んで、シリアスな部分を際立たせる。サンダンス映画祭で観客賞に輝いた温もりのあるエンターテインメントとなっている。
――この作品が3作目ということを伺いましたが。
マリアム・ケシャヴァルズ監督(以下、ケシャヴァルズ監督):長編作品として劇映画は3本目です。ほかに長編ドキュメンタリーを1本撮っています。
――そのドキュメンタリーはどのような内容なのですか。
ケシャヴァルズ監督:“The Color of Love(原題:“Rangeh eshgh”)”(04)という、3世代の物語。ヨーロッパではかなりポピュラーで、未だにテレビで放送されています。それが最初の長編作品です。その前に実験映画を撮り、奨学金をもらってニューヨーク大学(NYU)に入学しました。2本の短編を作り、長編の“Circumstance”(11)と“Viper Club”(18)を作りました。
『誰がビンセント・チンを殺したか?』の監督のクリスティン・チョイがNYUの教授を務めていて、「脚本の書き方を理解するためには、まずドキュメンタリーを作ること」というのが指導方針でした。初めて作ったドキュメンタリーが『The Color of Love』でした。オブザベーショナル(観察的)・ドキュメンタリーから大きな影響を受けました。シネマ・ベリテのようなドキュメンタリーの手法のひとつです。
――クリスティン・チョイから得るものは大きかったのですね。
ケシャヴァルズ監督:クリスティン・チョイが担当していたのは3年間だけで、彼女はドキュメンタリーに大きな焦点を置いていたので、私のキャリアにも大きな影響を与えました。「ドキュメンタリーを編集した時点でもうフィクションになってしまう」と言い、編集した材料をいかに真実として見せるかを教えてくれました。

――これは自分の家族の話ですね。4作目に持ってきた理由はあるのでしょうか。
ケシャヴァルズ監督:私は映画の世界に入ろうとは全然思っていませんでしたが、9.11事件が起きました。自分の家族が世界貿易センタービルに近いところで仕事をしており、誰にも連絡が取れなくてすごく心配しました。私たちは生粋のニューヨーカーにもかかわらず、名前が「アリ」「ホセイニ」「モハメド」のようなイラン系なので、悲しむことを許されませんでした。
80年代の人質事件もありましたし、極めつけはトランプ政権の反移民政策でした。アメリカに移民した人たちのストーリーを、私のファミリーを通して描きたいと考えたのが、そもそものきっかけなのです。アメリカ・イラン映画でコメディを作りたかったのです。
――自伝を映画化するということで、どれぐらい忠実に描こうと思いましたか?
ケシャヴァルズ監督:全て真実に沿うというこだわりはありません。大部分は真実ですが、ちょっと順番が違うだけです。私は文学畑の出身で、書くことも教えていますが、真実を書くには物語のストラクチャー(構造)が重要です。ストーリーというのは、必ずしも起きた順番ではない。ストラクチャーを変えることで分かりやすい部分もあるのです。この映画の中では、母親と娘がいて、娘がナレーターのような形でストーリーをずっと語っていきます。娘は、自分の家族のことをもっと知りたい一方、母親は真実を隠したい立場でした。観客に分かりやすくするためには、順番を変えようと思いました。ただ内容として、とてもシリアスですが、笑える部分を設けました。
――最後に母親と本当の意味で共感しあうのは、「赤ちゃんができる」ということでした。
ケシャヴァルズ監督:初めて母親になって、母のサポートがないとできないことに気づきました。子どもを育てるということのありがたみも分かりました。当然ながらママになると、誰々ちゃんのママという、違うアイデンティティが生まれます。私がそういう体験をしたことによって、もっと自分の母親のことを知りたいと思うようになりました。
アメリカで生まれた私たちは「親は私たちのことを理解してくれてない」と思っていましたが、逆に「娘として母親世代のこと、かつての時代のことを理解しているのか」というのも、ひとつの気づきでした。一番強く感じたのは、13歳の母親役の女の子をキャスティングした時です。今、私の娘はそろそろ13歳ですが、母は13歳で訳の分からない田舎の町に連れて行かれて、子供を産んでいるわけです。それを考えた時に涙が止まりませんでした。私の母親はそんな苦労をしていたのだと改めて思いました。
――アメリカ人でありながら、イランっていう国を背負う特別な思いはありますか。
ケシャヴァルズ監督:いわゆる二重国籍という言い方になるのかと思うのですが、私はふたつの世界を知っています。アメリカ人でありイラン人でもある子どものころから両方の文化の良い部分に親しんで成長してきました。私はそれをマイナスに思っていません。アメリカの良さというのは、 自分をイタリア系アメリカ人、イラン系アメリカ人ということを堂々と言えることです。

――キャスティングは、イラン系の方を集められたんですか。
ケシャヴァルズ監督:ほぼ、イラン系ヨーロッパ人とか、イラン系アメリカ人の人たちをキャスティングしたんです。ただ、ひとつだけ13歳の頃の母親の役は、絶対イラン人の女の子にしたかった。レイラ役の子も同じように、イランから両親がアメリカに移民して、 私と同じようにアメリカで生まれて、イランの伝統文化というものを常に聞かされて育った子です。
――新作のお話について聞かせてください。
ケシャヴァルズ監督:今は2本、作品があります。ひとつは来年の春に開始する、母親役の女優が書いた脚本なんです。他人の書いた脚本で映画を撮るのは初めてですが、彼女が初めて恋に落ちた時のストーリーで、“Blue Flower”というタイトルの映画です。
もうひとつが、エピック(歴史もの)コメディです。『女王陛下のお気に入り』のような映画ですが、 19世紀のペルシャ王国の王様が主人公で、ヨーロッパ人がペルシャを侵略しようとする物語。でもコメディです。
インタビュー/構成:稲田隆紀(日本映画ペンクラブ)