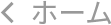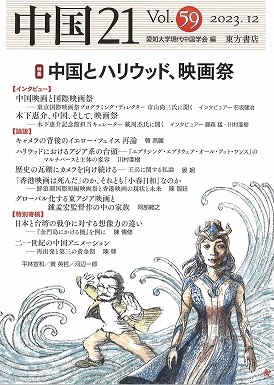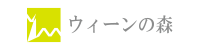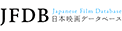東京国際映画祭公式インタビュー:
コンペティション
『開拓者たち』
フェリペ・ガルベス監督

20世紀初頭。チリ南部のパタゴニア地方に流れ着いた3人の男。表向きは地理測量のために領主に雇われた彼らだったが、実際の使命はその土地に点在して暮らす先住民の殺戮だった……。長年、隠されてきたチリの“黒歴史”を、荒涼とした大地を舞台に暴き出す骨太な作品。本作で長編監督デビューを果たしたチリ出身のフェリペ・ガルベス監督に、西部劇タッチのオープニングから自在に語り口が変化する手法の意図、そして、実際に事件が起きたフエゴ島での撮影の苦労などを伺った。
――“人間は、状況によってここまで残酷になれる生き物だ”と改めて心が痛みました。この史実を映画化しようとしたきっかけは?
フェリペ・ガルベス監督(以下、ガルベス監督):まず言っておきたいのは、「見せない」ほうが残酷なのです。昔に実際に起こった事実のほうが、もっと残酷だったと思います。そして、それを「知らない」あるいは「見せない」という状況のほうが、より残酷なことだと思います。これまでもチリの独裁政権の話になっても、彼らによって行われた犯罪の話は表面化しない。もっと非道なことがたくさん行われていたはずなのに、目隠しをしてしまう。そこが私には腑に落ちないのです。そういうことは見たくはないけれど、見せない、知らないほうがもっと残酷だと思いませんか?
――オープニングはエンニオ・モリコーネ風の音楽が流れ、西部劇のようですが、物語が進むにつれて表現スタイルが変わっていきます。その意図は?
ガルベス監督:私は歴史を学んだわけでもなく、人類学や人文学的なことを学んだ人間ではない。私は映画を学んだ映画人です。私がやりたいのは映画に対するリフレクション=内省、あるいは振り返りなのです。西部劇というスタイルの中に潜入して、内部から破壊するというか。私たちは西部劇の中でカウボーイが先住民を殺すというシーンを、1世紀にわたって何百万回も映画やテレビで見せられてきました。そういうジャンルはじつはプロパガンダではないかと思います。“カウボーイが先住民を殺すことになんの疑問も抱かず、驚きもしない感覚”を植え付けていく政治的な操作があったと思うのです。私は、それこそが暴力だと思います。
カウボーイによる先住民殺戮をエンターテインメントにして、それをプロパガンダに利用したこと自体が残酷極まりないことです。だからこの作品で、今も人気の高い西部劇というジャンルに疑問を投げかけたかったのです。オープニングで西部劇の音楽やコードを使って潜入して、徐々に西部劇というジャンルを裏切り、どんどん違うスタイルに歪めて、最後は放置して非難するという。
――雄大な自然の映像に圧倒されました。
ガルベス監督:この映画では自然というものを背景とは捉えずに、登場人物のひとりだと考えました。なぜなら、この映画の中で風景、景色、大地そのものが、問題の根本にあるからです。あれだけ広大な土地なのにいろいろな文化が入り込む隙がない。映画の中でも、3人の男とひとつの家族しかいないのに、全部がそこに収まる余地がなくて諍いが起こります。なので、あの過酷な自然というのは登場人物であって、この問題の中心であると捉えました。
――実際に事件の起こったフエゴ島で撮影を行ったそうですが?
ガルベス監督:驚くべきことに、いまだに事件当時と同じ領主メンデス家の所有地だったのです。いわゆる私有地ですから、撮影するにもいろいろな条件をクリアしなければなりません。でも一番大変だったのは、気候の急変です。春に撮影をしたのですが、30分ごとに天候が変わる。晴れたと思ったらすぐに曇って、雨や雪が急に降ってくるし、風もすごく強い。
そもそも「フエゴ」というのは炎という意味で、炎が燃え盛っている音と言われるくらい風が強い。ですから、現地では自分たちが計画したものを撮るのではなく、自然の状況に適応しながら撮る感じでした。今どういう状況なのかを見極めて、決して自然に逆らうことなく撮っていきました。
――映画化の実現までのプロセスでいちばん難しかったのは?
ガルベス監督:やはり資金集めが何より大変でした。そりゃそうですよね。実績のない新人の建築家に設計図だけ見せられて、その家を買いますと約束してしまうようなものですから。脚本は最初の5年くらいでできていたのですが、信じてもらうまでに時間がかかり、結局、映画が出来上がるまで9年かかりました。着想からは12〜3年ですね。
でも、今ではあの9年間が良かったと思っています。なぜかというと、9年の間にいろいろな人についていろいろな仕事をして、他の監督はどういう過ちを犯したのかという技術的なものを多く学べたからです。技術的に成熟すると同時に、脚本も少しずつ練り直して、テーマや問題を精査していきました。そういう準備期間があったので、結果的に私自身が納得できる作品に仕上がったのだと思っています。もし9年前に撮っていたら、たぶん悔いが残る作品になっていたでしょう。初めての映画にしては、野心的だったと自負しています。

――次の作品の準備は進んでいますか?
ガルベス監督:もしかしたらね。今回の映画は、チリの消されていた歴史のページを西部劇というジャンルに潜入して描いきました。私は消された歴史のページをもっと描きたいという思いと、今作のようにそのジャンルの中に潜入して内側から疑問を投げかけたいという欲求があるのです。
エンターテインメントだけど、じつは政治的なプロパガンダの一環として使われてきた映画やジャンルは、西部劇以外にもすごく多いと思っています。だから、今後もそういうテーマをやってみたいですね。それに第二次世界大戦後のアメリカとソ連の“冷戦”についても描きたいと思っています。まずはこの東京国際映画祭でグランプリをいただけたら最高ですけどね。
インタビュー/構成:金子裕子(日本映画ペンクラブ)