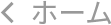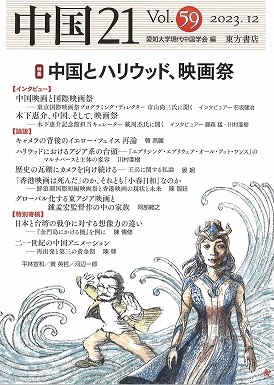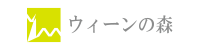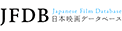東京国際映画祭公式インタビュー:
アジアの未来
『ロシナンテ』
バラン・ギュンドゥズアルプ(監督/脚本)、デニズ・イェシルギュン(プロデューサー/脚本)

失業中の夫、健康保険勧誘のオペレーターの妻、そして聴唖の息子。経済的に厳しい状況に追い込まれた一家は、唯一の乗用車である単車「ロシナンテ」号を糧に、バイクタクシー業を始める。ところがそのバイクも盗まれてしまい……。本作『ロシナンテ』で長編監督デビューを飾ったバラン・ギュンドゥズアルプ。広告、写真家としてのキャリアからか、“格差社会”をテーマにしつつも、明快かつスマートなまとめ方で、希望あふれるホームコメディに仕立て上げた。
――長編デビューおめでとうございます。まずこの作品のインスピレーションは何から得たんでしょう?
バラン・ギュンドゥズアルプ監督(以下、ギュンドゥズアルプ監督):首都イスタンブールの雰囲気から得ています。そもそもの発端は、5、6年前。バイクタクシーのアプリに興味を持ったのがきっかけです。このアプリを使う人、そしてバイクタクシーを営む人はどんな人達なんだろう、ということに興味を持ったんです。
またそのころ、私はストリートでいろんな人々の写真を撮っており、被写体になった人々と話す機会が多かったんですが、この映画の主人公たちのように苦しい思いをしている人の話などを伺うことがありまして。それで脚本家のデニズさんと、これらのアイデアを長編映画にしてはどうかと考え始めました。

――では、この主人公たちは、現実にいた人、ヒアリングした人がモデルになっているんでしょうか?
ギュンドゥズアルプ監督:誰かひとり、ということではありませんが、お話を伺った人々の経験談がもとになっていることは間違いありません。それに、脚本化に向けて動き始めてからは、私がモーターバイクの乗客になって、そのドライビングの経験、ドライバーのお話などを、毎日デニズさんに電話で話してアイデアをためていたんです。もちろん、それらはアイデアとして使うだけで、完全にフィクションとして作った部分もあります。
デニズ・イェシルギュン(以下、イェシルギュン):私がまず脚本を書くうえで注目したのは、主人公夫婦のキャリアについてでした。トルコでは、ホワイトカラーの仕事をしていた人たちの中でも、経済的中間層の人々がいなくなっているんです。じつは私達ももともとはホワイトカラーの仕事をしていたので、その状況が手に取るようにわかりますし、そういった人々が大都会で一生懸命、必死に生きていこうとしている姿が反映されています。また彼らの息子の設定についても、私達の身近な例なんです。
じつは私達には長年の共通の友達がふたりいるんですが、そのふたりとも聴唖のお子さんがいらっしゃるんですよ。突飛な設定に見えるかもしれませんが、全く突飛ではなく、現実に、しかも身近にいる人達をモデルにしてるんです。

――劇中で、彼らはすごく簡単にバイクタクシー業を始めちゃってますが、実際にはこんなに簡単にはできませんよね?
ギュンドゥズアルプ監督:もちろんそれには訓練があり、訓練を受けた者だけが開業承認を受けられるシステムがあるんですけど、それを入れると長くなってしまうのでカットしました。おそらく違和感があるとしたら奥さんのほうですよね。旦那さんが急病で、奥さんが代わりに運転手をするシーン。あれは、旦那さんが登録しているシステムを一時拝借しているだけなので、かたくなにヘルメットをはずさず、夫になりすまして運転手をしているんです。そういうことも、リサーチで分かったことで、実際にあることでした。
モーターバイクの運転手さんのほとんどは、もともとはホワイトカラーの仕事をしていた人たちなんです。元々のキャリアがあった人たちだけど、その歯車から抜け落ちてしまった人。または、ある一定の年齢に達して上のポジションにはつけずにキャリアが止まってしまった人。そういう方々は、とにかく給料は足りないし、将来も保証もないという状態になってしまい、やむなくバイクタクシーの業界に移ってきたんです。
――バイクタクシーの運転手は、まるで社会の出口のようだと。
ギュンドゥズアルプ監督:そこでイスタンブールのような巨大都市の特性が関わってきます。あそこまでの都会だと、タクシードライバーが奴隷のようになっていくんです。やむなく移った業界ではあるものの、ひたすらずっと稼働していかなきゃいけない。おまけに交通状態も大変危ないですし。でも、稼ぐためには、お客さんからの評価を集めなきゃいけないので、ひたすら稼働しなきゃいけない。いきすぎた資本主義の結果を表しているんです。
――それがエリートの集中する都会だと顕著に出る、と。
ギュンドゥズアルプ監督:教育を受けた人々、そしてキャリアもある人々が私たちの社会においてとても追い詰められた状態になっている。いわばもぬけの殻になっているんです。パンデミックの前からこのテーマはありましたが、パンデミックを経験したことで、世界中で彼ら中間層が先を開きようがない状態に陥ってしまいました。いわゆるプロレタリアです。階級意識はなく、自己責任主義。現状を打破するためにみんなで組織を作って戦うという発想がない。また、十分な教育を受け、キャリアを持ってるけれど、それに見合うだけのお給料あるいは、承認も得られていない。
この奥さんも、建築を学んだのにコールセンターのお仕事をしてますよね。夫の方も自分の職業にあった仕事が見つからなくて、それに見合うだけのお給料の仕事を見つけられないでいる。その逃げ道がバイクタクシー。そこには将来と保証がありませんが、だからといって彼らはもう希望がないとか、人生真っ暗闇とか、絶望はしていない。
それって、多かれ少なかれ、どんな人も持っていることじゃないでしょうか。絶望する前にすがりつく先を皆さん知ってるんです。それが家族なんですね。暗くはならないように家族と手を取り合い、すがって生きていくことができる。それを、ラストシーンに込めています。あのシーンで、夫婦はようやく希望を見出すことができたんです。
――絶望を皮肉ではないコメディにして、明るい未来の指標を作る。どん底に落とそうと思えばいくらでもできたんですから。非常に難しいことだったと思います。
ギュンドゥズアルプ監督:トルコには我々新人監督をサポートする文化観光省があり、私は2020年にサポートをもらいました。が、皆さん御存知の通り、その年にパンデミックがあってロックダウン。ただ、その1~2年間、この脚本を練り上げる猶予ができたんです。作るごとにより良いものに仕上がっていき、パンデミックの時間をアドバンテージとして使うことができました。
デニズさんと一緒にモーターバイクに乗ったり、ツーリングをしながらロケハンをしていました。その間も頭の中では映画を撮っている気分でしたね。このストーリーに着手したのは2017年でしたが、それから6年かかってようやくお披露目することができました。
――3人のキャスティングは、パンデミックの間にされたんですか。
ギュンドゥズアルプ監督:じつはみな私の近しい人たちでしたので、パンデミックの前から決めていました。夫のサリ役のファティヒ(・ソンメズ)さんは、私が制作した短編映画に出演していただいていたので、もう10年くらいの付き合いです。子役のジャン・デミルさんは、私が撮った広告に出演してくれたことがあったのでお声がけしました。彼はその広告の仕事のとき、人生の中で一番素敵な日だった、と言ってくれてたんですよね(笑)。そのことを、ある時ふと思い出しました。
エムレ役は本作にはとても重要ですし、やる気はもちろん、集中力をもっていないとできません。それで私の現場を楽しんでくれたジャンさんにしようと決めました。もちろんテストもしましたよ。試しに撮影してみたらもうバッチリ。奥さんのアイシェ役のニライ・エルドンメズさんも、2017年から知り合いでした。このプロジェクトが始まる時からこの役は彼女にやってもらおう、と決めていたようなものです。
イェシルギュン:ファティヒさんは、バイクタクシーの運転手を理解したいということで、しばらく実際にやってくれたんですよ。

ギュンドゥズアルプ監督:そうそう。彼がドライバーをやってみて分かったことは、お客さんとおしゃべりをすることによって、ドライバーもかなり影響を受ける、ということでした。ただ人を乗せて目的地に連れて行く、というだけではない仕事だ、と。たとえば、目的地まで連れて行ったら、お客さんからちょっとお茶を一緒に飲まないか?と誘われたりするんです。思い出話やお客さんの体験をシェアしてる職業ということを理解したうえで、この役に挑んでいただきました。
――単調かと思いきや、人情味ある仕事ですね。その交流もあらゆるところで撮影できたのは、イスタンブールがロケ撮影に寛容だから?
ギュンドゥズアルプ監督:いえ、イスタンブールではこの手の映画を撮ることはとても難しいんですよ。テレビシリーズの撮影はすごく盛んで、世界一・二のロケ地だとも言われ、市民の皆さんも撮影に慣れてらっしゃる。けれども、インディペンデントやアートハウスの映画の場合はそうはいきません。許可どりや予算などの手続きが非常に煩雑で……。私はストリートで写真を撮っていたので、その時の経験を生かして、即興的に撮影していくことにしました。
インタビュー/構成:よしひろまさみち(日本映画ペンクラブ)