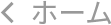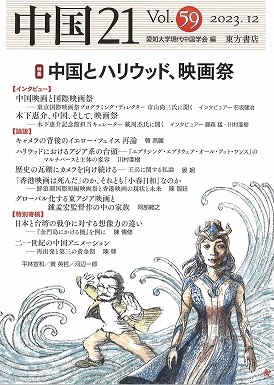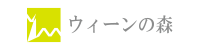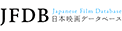10/24(火)Nippon Cinema Now『小学校~それは小さな社会~』上映後、山崎エマ監督をお迎えし、Q&Aが行われました。
⇒作品詳細
山崎エマ監督(以下、山崎監督):皆さま、この映画の初上映であるワールドプレミアにお越しいただきありがとうございます。この映画を作りたいと思い立ってから9年が経ち、ようやく今日を迎えられたことに涙が出そうです。この映画の制作にあたっては紆余曲折がありました。まず、撮影をさせていただける学校を見つけるまでに5年かかりました。そして、今日この会場にも来てくださっている世田谷区教育委員会の皆さまにご協力いただき、やっとの思いで学校が決まりましたが、その後のコロナ禍によって制作に関わる活動を一度止めることになりました。そうした状況において、制作を続けるべきか、一旦中止をし5年後、10年後にまた改めて制作を再開するべきか、たくさん悩みました。悩んだ挙句、私が以前から制作したいと思い続けていた日本ならではの学校をテーマにした映画には、コロナ禍で撮影するからこそ撮ることのできる、その瞬間を歴史として残せるという、より強い意味を持たせられるのではないかと考え、2021年から2022年にかけて実際の撮影を行いました。150日間かけて撮影し、合わせて700時間分にもなった映像を、そこから1年以上かけて編集し、やっと今日という日を迎えられました。今日ここには、この9年間さまざまな場面で共に歩んでくれた、夫でありプロデューサーであるエリック・ニアリをはじめとして、カメラマンの加倉井和希さん、音声をやってくれた岩間 翼さん、そしてさまざまな関係者の皆さん、出演してくださった子どもたちや保護者の皆さま、関係者の皆さまが揃うなか、東京国際映画祭という素晴らしい場で上映することができたことを本当に嬉しく思っています。映画を制作したかった理由というのは後ほど改めてお話させていただきます。この9年間、めげそうになったことは何度もありましたが、このような映画は、後にも先にも制作されることはないだろう、今やり遂げなければいけないという想いでおりましたので、無事今日を迎えることができ、とてもうれしいです。そしてご来場いただきありがとうございます。
司会:市山尚三プログラミング・ディレクター:とても長い時間をかけて作られたということを伺い、たいへん驚きました。まずは、このドキュメンタリー映画を制作しようと思われたきっかけをお話いただければと思います。
山崎監督:私は父がイギリス人、母が日本人で、自身は大阪で育ちました。日本の小学校に通い、卒業してからはインターナショナルスクールに入学しました。その後は、大学進学のためにアメリカに行き、徐々にアメリカの文化に馴染んでいきましたが、小学校教育に関しては、完全に日本で学びました。その後、社会人になり、特にアメリカ・ニューヨークで仕事をするようになった際に、自分の人生を改めて振り返ると自身の日本人としてのすべては日本の小学校で学んだことに由来しており、小学校を原点として、ある意味において自分の強さが生まれたのではないかと思うようになりました。子供たちが役割を与えられ掃除したり、給食配膳をしたり、放送委員をしたり、石鹸を換える係だったり、靴箱を揃える係だったりするのは日本だけです。そのような教育のあり方も含めて海外の人にも知っていただきたいですし、日本はなぜこのような教育をするのかと疑問に思う方々には、その疑問の答えとして、寿司やアニメや忍者といった分かりやすい文化ではなく、学校や教育システムの中にあるのではないかということを自分なりに表現することで考えていただきたいと思いました。教育の場を見れば日本社会のことや、これからのことを考えることもできます。その土俵としての小学校を撮影したいと思ったのがきっかけです。
Q:驚いたのが、小学校1年生の入学式を撮影しているシーンで、子どもたちがまったくカメラを見ていないことです。どのように撮影したのかお伺いしたいです。
山崎監督:映画の構成上、撮影初日から絶対に使うであろうシーンを必要とする一方で、学校の制限として4月1日になるまでは、どの先生が担任になるか分からなかったり、それまで保育園や幼稚園で関係性を育んできた子どもたちが新1年生になり、どのようなクラス分けになるかも分からない、といった制約に関する難しいことも多くありました。ただ幸いに新1年生にとって学校とはマイクやカメラがある場所なんだ、と認識した程度だったのではないかと思います。最初の1年間は初日から撮影クルーがいた環境とは反対に、2年生になってからは「あれ?カメラはどこに行ったんだろう?」と思うほど学校の一部として私たちが溶け込み、先生なのか誰だか分からない、単に大人と認識してくれていた気がします。そのような状況でも、子どもの目線から撮影したいという想いがあったためCANON EOS C70というかなり小さなカメラを使い、できるかぎり教室の中にカメラマンが溶け込み、監督の私でさえどこにいるか分からないほどの動きをしていました。子どもたちにとって教室に机があるのと同じように、カメラがそこにあったのだと思います。初日からそうした自然な環境を作れるよう工夫しました。音声に関しても同様に、日本では珍しいかもしれませんが、最新の小型ピンマイクを今回は使用しました。日によりますが大体10~16本ほどのピンマイクを先生や子どもたちに付けなければ、このような音声は録音できませんでした。職員室にピンマイクを置いて、先生たちには毎朝自分で装着してもらうという環境をつくりながら、子どもたちについては保護者から許可を得たうえで、このようなシーンを撮る前後に付け外すようにしました。この映画はナレーションのない、音と映像のみですので、学校という場所を主人公として、そのなかにいる人間をできるだけ観察して捉えるためのあらゆる工夫をしました。
Q:映画はソーシャルドキュメンタリーというジャンルで、製作国として、フィンランドとフランスも名を連ねています。監督はこの作品を、日本の子供たちに向け日本の教育の姿を見せるために製作したのか、もしくは海外の方々に向けて、日本の教育のあり方を発信をする目的だったのか、どちらでしょうか。
山崎監督:1番の目的は、海外に向けて日本の教育を伝えることです。私は、日本と海外を行き来する生活の中で、日本と海外の両方をフラットに比較できることが自身の強みだと思っています。日本の教育では、給食係や電気係など小さなことにも子どもたちに責任を持たせる仕組みができており、それを少しも変わったシステムだとは捉えていませんが、このような姿勢を海外に伝えることで、日本の優れた教育システムを理解していただけるのではないかと思い製作しました。そして、それに対する海外の方々の反応を通じて、日本の方々にも日本の教育システムの素晴らしさに気づいてもらえるのではないかと思いました。もちろん完璧なシステムではないですが。このような日本の教育システムに対してフィンランドやフランスでは、作品の完成前から面白みを感じていただいていたようでした。日本では先生になるということが非常にチャレンジングであることや、コロナ禍での学校運営の苦労を描くことで海外の方々に、日本の取り組みから何か学ぶことがあると感じてもらいたい、と思いました。
また、日本の子供たちは、自分たちの人生には限界があることを前提に学校の中において自分の役割を果たすことに注力しています。一方、アメリカでは「限界などはない」「限界を取り外せ」という教育がなされています。どちらが優れているというものではないと思いますが、日本の教育はある意味、集団生活の中での学びを重視していて、それ自体がネガティブな捉えられ方をすることも多いのですが、そのまま世界の方々にも見てもらいたいと思うとともに、日本の方々にも見直してほしいと思いました。
Q:同様の作風の映画として北アイルランドの学校の様子を紹介した『ぼくたちの哲学教室』(21)という映画があります。その映画では子供同士の争いやケンカが、土地柄もあってか色濃く描かれていたのですが、本作ではネガティブな要素はあまり描かれていないように感じました。そうした側面は製作時にどう捉えられていたのでしょうか。
山崎監督:同じ学校にほぼ1年間通いつづけカメラを回すなかで、海外の方々に見てほしいところや日本の方々に考え直してほしいことに焦点を当てながら素材選びをしていました。もちろんストーリーとして魅力的なものにしなければならないし、多様な要素が凝縮された作品にしたいと思いながら取り組んでいました。さまざまな映画作りの方法があると思いますが、ご質問頂いたようなネガティブな要素に敢えてスポットを当てることはしませんでした。自分の中で描こうとしていた内容をカメラを通して集めたり、あるいは想定していなかったような出来事が起きたときにそれを真正面から捉えたりしながら、1つの作品に仕上げることだけを考えていました。ドキュメンタリーというのはドキュメンタリーなりの難しさがあって、そもそも事前にアイデアや規格がないと始まらない。一方、撮影環境という枠の中で出会う子供たちや先生との出来事や彼らの成長、心の変化に向き合いながら自分自身が責任をもって視点を入れ込み、100分程度の映像に整理したうえでメッセージを込めなければならないのです。今回も、事前にフォーカスしたいと思う内容はありましたが、結果としてご覧頂いたような作品になりました。もう一言だけ補足させていただくと、ニュースなど報道レベルでの話において日本の教育現場では教員不足や労働環境の悪化が叫ばれています。だからこそ丸々1年間、実際の学校現場の中で、突如として映画製作班が入り込んでいき映画を製作したということは、この先中々できないトライだったのではないかとも思っています。製作を進めていく段階においてもちろん、日本の学校教育はこうあるべきだというメッセージを込めることもできたのでしょうけれど、作品を観る人に解決策を委ねることを含めて、いろんな人に関心を持ってもらいたいという思いがありました。学校は日本の未来や社会を作る場であるし、今後どうあるべきかをさまざまな人が議論している中で、現状はこうなのだ、ということをありのままにお見せしたいと思いました。幸運にもそうした現状を伝えることができる立場を得て、そもそもどういった現状を伝えればよいのか、子供の教育の中にある尊さや葛藤に全力で向き合っている先生方を真正面から捉えて海外に向け伝えたい、そう思ったのです。
Q:3つの学期ごとに主人公を変えて作品が作られていますが、これは最初から主人公を決めて撮影していたのでしょうか?もしくは撮影を行った後で誰かを主人公に決めて作品を組み立てたのでしょうか?
山崎監督:小学校には子どもたちは1,000人以上いました。どの子が撮影期間中にどう変化していくのか全く分かりませんでした。40~50人程度の子どもの保護者の方々にも撮影に先立ってお会いしましたが、それこそ撮影の間に何が起こるかもわからないし、保護者の方々に撮影の許可を頂けるのかどうかすら分からなかったのです。また実際に撮影した映像は作品に使われた量よりもはるかに多いのですが、あくまでもこの作品の主人公は学校そのものであり、その中に多くのアンサンブルキャストがいて、先生や子どもたちの間のバランスがどうあるべきかを考えながら撮影と編集をおこなっていきました。さまざまなキャラクターたちに触れる中で最終的にどのようなメッセージにするべきなのか、個々人の個性と作品のメッセージの間を行き来しながら取り組んでいました。