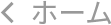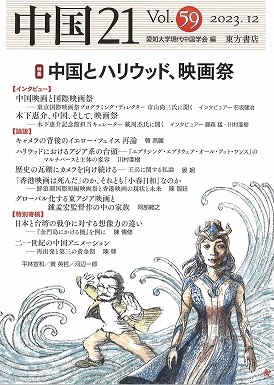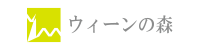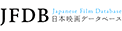トニー・レオンが来日、ホウ・シャオシェン監督『悲情城市』、ウォン・カーウァイ監督『2046』の思い出語る

トニー・レオン ©2023 TIFF
開催中の第36回東京国際映画祭ワールド・フォーカス部門でウォン・カーウァイ監督の『2046』が上映され、主演のトニー・レオンが来日し、トークを行った。
ウォン・カーウァイ監督作『グランド・マスター』(2012)でのプロモーション以来10年ぶりの来日となった。若き日は香港映画のアクション娯楽作で頭角を現したが、1989年製作、台湾のホウ・シャオシェン監督がベネチア映画祭金獅子賞を受賞した『悲情城市』に出演、ろうあの青年を演じ世界的な注目を集めるようになった。
『悲情城市』出演の経緯をこう語る。
「映画に出て間もない頃、いろんな映画に出て、いろんな経験をしたいと思っていた時期で、ホウ監督からお声がけいただき、いい機会だと思ったのです。しかし、この役を引き受けた当時は台湾の歴史をあまり知らず、勉強しなければなりませんでした。ホウ監督からたくさんの本をいただいて、準備をしました。私は台湾の言葉が話せなかったので、ホウ監督が口がきけない役柄を設定してくださいました。役作りの参考に、監督のお知り合いで、事故にあって話せなくなったアーティストの方を紹介してもらい、台北から6時間かけて台南に会いに行きました。表情やしぐさ、所作から勉強し、理解することができました。また、ホテルにこもってひとり本を読んだり、孤独に過ごすようにしました。話せない人の気持ちを実体験したかったのです」
『悲情城市』のような芸術映画に初めて出演し、現場で学ぶことが多かったです。演技を学んでいた頃、外国の芸術映画をたくさん見ていましたが、現場のことはわかりませんでした。ホウ監督のおかげで文学が好きになり、孤独になって本を読んで、文学作品の中から登場人物の描写や情感から、芸術に関する認識が深まったと思います。また、撮影現場ではプロの役者以外の素人の方もたくさんおり、彼らのリアルな演技に驚きました。これまでの自分の演技が半信半疑になるほどで、どうすれば彼らのように自然に演じられるのか考えさせられ、演技についても、大きな影響を与えられた作品です」
1990年製作の『欲望の翼』から長年タッグを組むウォン・カーウァイ監督との出会いについては、「ちょうど自分の演技に対しての壁にぶつかっていた頃、ウォン監督に出会い、『欲望の翼』に出ました。ウォン監督は私の演技のどこが良くないのかをわかっていました。共演したマギー・チャンは2、3テイクくらいでOK出るのですが、私は20テイク以上も繰り返しました。ウォン監督は、私の演技は技巧的だと指摘し、それを壊してくれました。完成作で自分の演技を見て、ウォン監督はすごさがわかりました。役者の良いところを引き出すことに長けているのです。ウォン監督とはそれから20年間一緒に仕事をしています」と明かす。
さらに、レオンとウォン監督の若き日のエピソードも披露してくれた。
「夕食後に監督と雑談をします。その中で、監督はいろんな音楽や文学を紹介してくださり、その世界に入り込んでいきました。ある時、『ノルウェイの森』を紹介されて、直子がワタナベを見送るときに、直子の表情については書かれていません。その表情はどんなだったのか――そんな話をよくしていました。ウォン監督と2、3作品で仕事をした後、彼のやり方、撮りたいものがだんだんわかるようになりました。ウォン監督との出会いからこの20年間、2度目の訓練を受けている気がします。監督と監督のチームは素晴らしく、美術のウィリアム・チャン、撮影のクリストファー・ドイル。素晴らしい役者たち、彼らからも学ぶことが多かったです」
「ホウ監督の『悲情城市』に参加した時、どうすれば素人のように自然に演じられるのか? それをずっと願っていました。ある意味でウォン監督の現場でそれがかなった気がするのです。ウォン監督の作品に脚本はありますが、我々俳優は見せてもらえず、全体の物語と、自分の役柄についてのみ教えられ、それに関して指導はありますが、どのような物語になるかは知らされないのです。それはウォン監督ならではのユニークなやり方。撮影現場で、役者の演技やカメラの動きなどに関して、余裕を残しておきたいのだと思います。役者に情報を与えすぎないこと、情報が多すぎると役者も構えてしまいますから。それは監督は欲していないのです。ですから、毎回撮影はアドベンチャーのようです」
『2046』(04)は、1960年代後半の香港が舞台。作家のチャウはかつて愛したひとりの女の思い出から逃れるように自堕落な生活を送っていたが、近未来小説を書き始め、現在と未来が交錯し始める……という物語。木村拓哉も出演している。今回の上映で本作を選んだ理由をこう語る。
「この作品は私にとって特別な作品です。この物語は『花様年華』とつながっている。ある意味続編で、私が演じたのは同じ人物です。しかし、違った演技で、過去を忘れて新しい暮らしに向かう主人公の姿を見せてほしいと監督に言われました。監督は1本の映画を完成させるのに時間がかかりますし、私もずっと同じ人物を演じるのは大変なので、ひげを付けさせてくださいと監督にリクエストをしましたが、却下されました。それでも絶対必要だと言い張りました。そして、カンヌ映画祭でのプレミア上映後のパーティで、監督から『やはりひげがあって正解でしたね』と言われました。役者にとっては、何らかのきっかけで役に没入できるのです。私はそう思います」と自身の提案によって、作品に良い結果をもたらしていたようだ。
「ウォン監督の現場では毎回新しい試み、チャレンジがあり、役者にとっても新しい体験がある」という。「演じた役柄が抜けきらないことはないのか?」という質問には、「役者をやりはじたときは、役から離れるのが難しかったことがあります。しかし、普段の日常を暮らし、自分に戻っていきます。それは習慣のようなもので、役を演じる時は長い時間がかかって、離れる時にも時間がかかるのです」と回答。
国際派俳優として今後の展望を問われると、「さまざまな国、地域、異なる製作チームでの仕事がしてみたいです。ヨーロッパ映画にも出てみたいと思っており、来年ドイツで撮影する映画に出演することが決まりました。今は、8カ月間の準備期間。たくさんの本を読んでリサーチをしています」と語った。
第36回東京国際映画祭は、11月1日まで開催される。
新着ニュース