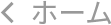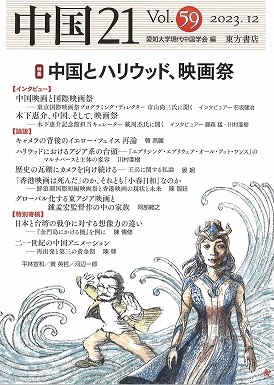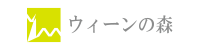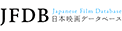世界各国の女性映画ジャーナリストたちがトーク「女性だからこそ、女性が置かれた状況を理解でき、書くべきだと思う作品が増えている」

潜在的なジェンダーバイアスのキャリアへの影響について、経験を語り合う
第36回東京国際映画祭の、女性映画ジャーナリストたちによるトークイベント「映画ジャーナリズムにおける女性のまなざし」が10月26日、有楽町 micro FOOD & IDEA MARKETで開催された。
本イベントでは、さまざまな国で活躍する女性映画ジャーナリストたちが、各国の映画メディアにおけるジェンダーパリティ(ジェンダーの公正を実現するための統計的な尺度)の現状や今後の展望について、座談会形式で語り合った。本映画祭のフェスティバルナビゲーターを務める安藤桃子監督が、モデレーターを務めた。
最初のトピックは、それぞれの国における女性ジャーナリストを取り巻く環境の変化について。恩田泰子氏(読売新聞編集委員)は、日本の新聞社における女性記者の割合は増えつつあるという。そのうえで、「いまはウェブなど書く場所が増えて、プロフェッショナルじゃない方も、プロフェッショナルの方も書くようになって、それぞれの視点があります。誰が、どこで書いているかが見えにくくなっています」と語る。ウェンディ・アイド氏(イギリス、映画評論家)は、「イギリスの現状としては、記者は多いにせよ、プロとして活動している方は少ないです。その仕事を主な収入源・キャリアとして全うしていくのが難しい。まずは、「ご自身の声を大衆に聞かせる」ところから始める。SNSなどのプラットフォームがあるので、皆が声を上げやすくなっている環境はあります」と分析した。
続いて、ナダ・アズハリ・ギロン氏(フランス/シリア、映画評論家/ライター)は、「ジャーナリストとフィルムクリティック(映画批評家)というふたつの分野があります。2000年頃、私の周囲で映画批評を書いている方は2~3人しかいませんでしたが、ジャーナリストは女性も多かったです。当時から比べるとかなり進歩して、女性の映画批評家でプロとして仕事をされている方が増えて、フランスでは全体の37%いるという認識です」と明かす。
そして話題は、「批評家とジャーナリストの違い」へ。アイド氏は、「映画批評家は、映画のレビューを書く人。ジャーナリストは、批評に加えて、インタビューをしたり、特集記事を書いたりします。批評家は、映画製作者とはある一定の距離をとらなければならないですから、あまり関われないという難しさはあります」と説明。セシリア・ウォン氏(香港、映画評論家/キュレーター)は、「香港では、批評家とジャーナリストの境界線がなくなってきたと思います。やはり、オンラインのプラットフォームがたくさんできたことで、自由に意見を発表する機会が増えたことが、その要因だと思います」と、現状を伝えた。
安藤監督はここで、「女性映画記者は、映画の女性主人公の視点を理解できるため、高評価につながることがある」「日本では女性映画監督が非常に少ない。2000年~21年に劇場公開された、興行収入10億円以上の実写邦画796本のうち、女性監督作品は25本、3.1%」というふたつのデータを紹介。そして、「ご自身が女性記者として、女性としての視点が役立ったと感じたエピソードはありますか?」と質問を投げかけた。
アイド氏「どんな視点も主観ですから、「男性の視点だから、女性の視点だから」という型はないということを、前置きとして言っておきます。そうは言っても、それぞれの主観はあります。往々にして女性は、男性が作った映画における女性像は何か理想的な、幻想的なものであるという違和感を抱くことはあります。例えば、ウッディ・アレンの映画などはそう感じますね」
ギロン氏「若い頃からずっと、アラビア語の映画を見てきたのですが、女性が被害者として描かれることがとても多いです。それを見てきた私は、「何かを変えなければいけない」と思い、フェミニストになりました。ほとんどの場合は、監督の性別が作品を左右することはないと思います。例外は、子どものことを描いた作品。女性であるがゆえに、女性としての視点を持つことができた作品もあるんじゃないかなと思います」
恩田氏「男性の視点や女性の視点というものはあると思うんです。ですが、これまでのキャリアを振り返ると、「女性だから」よりも、「人間だから、こういう見方をしている」と、性別の区別はなく見てほしいという思いが、どこかにあるわけですよね。自分はあえて「女性だからこう見た」と強調することは少なかったんですが、最近は自由になってきた。それは、女性の視点を感じさせる、女性を取り巻く状況をきっちりと描く作品が増えてきたからです。女性の私だから、女性が置かれた状況が分かるし、書くべきだと思う作品が増えている気がします。例えば、アリス・ディオップ監督の『サントメール ある被告』や、キティ・グリーン監督の『アシスタント』などです」
最後は、「性別が原因で、キャリアが困難になった経験」というテーマについて、意見が交わされた。ギロン氏は、「女性はもっと仕事ができます」と証明するのに、まだまだ時間を要するというのが、周囲の人々の見方です。こと映画批評家に関しては、当初はかなり偏見がありまして、「時間が余っているから、適当にやっているんだろう」という見方が強かったんですが、そういう見方も、近年は変わってきました」と振り返る。
アイド氏は、「駆け出しの頃は、いろいろあったにせよ、リアルタイムでは気付いておらず、いま振り返ってわかることがあります」と述懐。「あからさまに「キャリアを邪魔してやろう」という動きはなかったにせよ、やはり潜在的なジェンダーバイアスがありました。例えば男性には、アートフィルムの大作の仕事が与えられる一方で、女性である私は「子猫や靴について書いて」と言われるんです。女性は、知的に重みのないものを任せられる傾向があるんです」「もうひとつの問題は、男女間でやはり給料が違う。男性の方が多く支払われている現状があり、気付いた時は言いにくいと思いますが、声を上げることが大事だと思います」と指摘した。
ウォン氏は、アイド氏の意見に賛同しながら、「私も駆け出しの頃、こんなことがありました。ギャング映画とカンフー映画の、ふたりの有名男性監督にインタビューをしたときに、「君のような若い女性には、俺らのやっていることは分からないだろう」と立ち去られてしまったんです。そういう経験をしたので、これからインタビューを重ねて、キャリアを積んでいくことができるのかと疑問に思いました。何年も経った後、再び彼らにインタビューをしたときは状況が変わっていて、活発に意見を交わすことができました」と、エピソードを語る。
ウォン氏「やはり男性監督の間では、女性への認識のバイアスがあるのだと思います」
恩田氏は、「皆さんがおっしゃっているような、ふんわりした性差別、女性に対するバイアスを乗り越えるには、仕事で証明するしかないと思います。それと同時に、悪く思われないように、和やかに接する努力もしてきたんですが、無駄だったかなと。若い方たちにはそういうことに時間を割かず、一生懸命働けばいいんじゃないかなと思います」と、エールをおくった。アイド氏も、「これから批評家を目指す方へのアドバイスとしては、とにかくいろんな人と話してつながることですね。この職業の期待値を精査して、自分のサポートシステムを作ってください。メンターを見つけてください。このコミュニティの一員となってください。コミュニティの人々が、皆さんをサポートしてくれます」と、力強いアドバイスで、トークセッションを締めくくった。
第36回東京国際映画祭は11月1日まで、日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区で開催。
新着ニュース