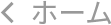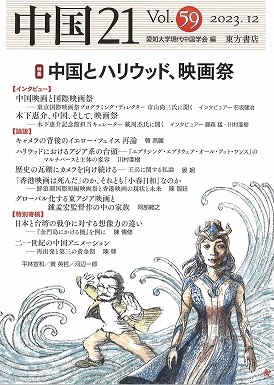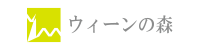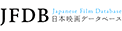10/25(水)小津安二郎生誕120年記念企画“SHOULDERS OF GIANTS”『父ありき 4Kデジタル修復版』上映後に、大澤 浄さん(国立映画アーカイブ 主任研究員)をお迎えし、トークショーが行われました。
⇒作品詳細
市山尚三プログラミング・ディレクター(以下、市山PD):これからこの映画の修復を行いました、国立映画アーカイブ主任研究員の大澤 浄さんにお話を伺います。
はじめに、私の話をさせていただきます。私は30年前、松竹株式会社(以下、松竹)の社員として、当時の東京国際映画祭で行われた小津安二郎生誕90年特集に立ち会いました。その際、松竹が所有する16ミリのマスターポジの音声に問題があり、35ミリにブローアップして修復しましたが、当時の技術では完全な修復には至りませんでした。ノイズを除こうとするとセリフまで消えてしまうため、多少の修復に留めるしかなく、本当に残念なことですが、音がほとんど聞こえないシーンもありました。しかし、本日上映されたものは、音声が本当にクリアになっています。さらに、新しい内容も追加され、現状では最長のバージョンを皆様にご覧いただくことができました。以前にもこの作品を観たことのある皆様にとっては、形式的にも内容的にも、大きな違いがある上映だったかと思います。それでは、大澤さんに、今回の修復の経緯についてお話を伺います。
大澤 浄さん(以下、大澤さん):国立映画アーカイブという国立の映画保存機関で働いております大澤と申します。まず、平日の朝からこれほど多くの方にお越しいただき、その中に若い方もたくさんいらっしゃることを、本当にうれしく思います。そして、小津安二郎の戦前の代表作の1つである『父ありき』の最新の復元版を皆様にご覧いただけたということを何より嬉しく思っています。
今回の修復のきっかけは、今年が小津監督の生誕120年ということで、松竹の藤井宏美さんから「一緒に何かやりませんか」とお誘いいただいたことです。『父ありき』のオリジナル版は1942年4月1日に公開された、94分のバージョンですが、それは今のところこの世に存在しません。というのも、その3年後、つまり敗戦後にGHQの検閲によって、7分間の映像が削られたからです。今まで我々が映画館やDVD、配信などで観ていたのは、検閲後の87分バージョンでしたが、これは、ところどころシーンが欠けているせいで、話の辻褄が合わない部分もありました。
1942年当時、国内で作った日本映画を国外に輸出しており、ここからは推測ですが、戦前の『父ありき』のプリントも満州をはじめとした海外に輸出されていたことと思います。そして、敗戦後にソ連軍がそれを接収して持ち帰り、現在のロシアの国立映画保存機関であるゴスフィルモフォンドに長く保存されていたのだと思います。その後、当時のソ連でペレストロイカが起こり、90年代には西側諸国との関係改善に向かい、映画保存機関にも西側諸国から調査の手が伸びるようになりました。
我々も、ロシアに大量の日本映画が保存されているようだという情報を聞きつけ、調査を行いました。その結果、それまで失われたと思われていた大量の日本映画を日本に持ち帰ることができたのです。その中に、戦前に輸出された『父ありき』の72分バージョンのプリントがありました。この72分の映像の中には、戦後検閲された松竹版にはない重要な場面が含まれていました。我々は、これを2000年ごろに何回か上映しただけでした。そのような経緯を踏まえて、この機会に松竹との共同事業としてデジタル化に踏み切り、ようやく両バージョンを統合することができました。
市山PD:僕も、おそらく2000年ごろ、国立映画アーカイブで観ました。その際、観たことがないシーンがあって本当に驚いたのですが、そこから復元まで20年ぐらいかかりましたね。その際にどこが変わったのかを、皆さんが知りたいところだと思いますが、いかがでしょうか?
大澤さん:まず、戦後に削られた部分ですが、幸いなことに松竹大谷図書館に台本が残っていたおかげで、削られた部分を確定することができました。それは、ほとんどが戦争に関するセリフで、音楽も含めて何か戦争を想起させるような要素がことごとく戦後のGHQの検閲によって削られていました。
劇中で、佐野周二が成人して秋田で化学の教師になりますが、一回目に笠 智衆と会い、二回目に会うときには丸坊主になっています。今日ご覧になった方はおわかりかと思いますが、一回目には、「今度、兵隊検査があるので、そのときにもう一回お父さんと会えますね」と。二回目には、兵隊検査のために上京していて、甲種合格を果たしているわけです。そこで、笠 智衆は、ようやく自分の務めは終わった、息子が甲種合格して立派な兵士としてここまで育て上げ、これで自分の父親、母親も兼ねた責任は終わったと感じるという、物語では重要な場面なのですが、以前のバージョンでは、兵隊検査や甲種合格というセリフが全て削られていて、一回目には「今度、会いましょうね」というようなセリフで、二回目にはいきなり丸坊主になっていて、甲種という言葉がなく、「検査どうだった?」「合格しました」というセリフになっていました。
市山PD:戦前のことをよく知っていると、理解できるでしょうね。
大澤さん:そうですね。検査といえば、兵隊検査だろうと。
市山PD:知らない人が観ると何のことかわからなかったわけですね。
大澤さん:そうですね。あとは最後の方で、笠 智衆が詩吟を歌う場面がありますが、これは、広瀬中佐という日露戦争の英雄が作った「正気歌(せいきのうた)」という中国の漢詩を起源とした忠君・愛国の歌を歌うわけですね。謝恩会では、笠 智衆のかつての教え子3人が応召中のため欠席しており、笠 智衆の息子である佐野周二も兵隊検査に合格して、やがては戦地へ行くだろうという場面ですね。
誰も口に出さないけれど、この中の人たちが将来戦死したり、あるいはその可能性が非常に高かったりするわけで、久しぶりの再会の場でありながら、もしかしたらこれが最後になるかもしれない場です。その、笠 智衆が「正気歌」を延々と吟ずるという場面を戦後版では丸々削られています。
市山PD:「海行かば」が流れていますが、あの音楽もなかったということですか?
大澤さん:そうです。さすがに場面としては画ごと削るとおかしいので、どのような処理をしたのかわからないのですが、サウンドトラックだけ削る処理をしたようです。
ですから松竹版では、無音のまま、佐野周二と水戸光子が夜汽車で秋田に向かうという終わり方になっていますが、音楽があるのとないのでは、全く意味が違う場面になっています。
市山PD:他の作品も含めて、戦後のGHQの検閲では、ネガごと廃棄したのでしょうか?
大澤さん:戦前も戦後も、まだテレビもなく、ましてやビデオもDVDもない時代ですから、基本的に、映画はひとたび劇場で公開されたら、それで寿命が尽きるということになります。そのときに消費される生鮮食品のような扱いだったわけですね。検閲で削らないと上映できないとなれば、ネガごと切ってしまうので、おそらくフッテージは廃棄されたのではないかと思います。
市山PD:日本には残っていないだろうということですね
大澤さん:ただ、幸いなことに、戦前にオリジナルからコピーされたプリントが部分的ではありますがロシアに残っていて、そこから再度フッテージをコピーする形で今回復元ができました。
市山PD:復元作業は非常に大変だったそうですが、特に大変だったことはありますか?
大澤さん:おそらく松竹さんもこれまでやったことがない復元かもしれませんが、基本的に1カットに違う素材を混ぜることはやらないですよね。
注意深い皆さんはお気付きになったかもしれませんが、佐野周二が甲種合格して、まだ禿があるなという場面ですが、よく見ると1つのカットの途中で、ちょっと異なるフッテージに変わっています。傷の出方や濃度とか、輪郭強調が変わっていて。ですから、それは同じカットの中で、我々が持っていたロシア由来のプリントと、松竹さんが持っていたマスターポジ、その2種類の素材を組み合わせて復元しています。
基本的には、画像については、松竹版16mmのマスターポジを、音については、我々が持っている35㎜のプリントを使っています。ただ、場面によって、一方に欠けていて、他方にはある画や音があり、結局、松竹版の画と音、我々が持っているプリントの画と音、合計4つからの組み合わせがあり、それを場面ごとに一番いいのはどの組み合わせかということを模索しながら追及していきました。おそらく、これは今までやったことがないのではないでしょうか。
市山PD:普通に考えると、2つのうち良い方のカットをつなぎ合わせますが、同じカットの中で異なるバージョンをつなぐというのは聞いたことがないですね
大澤さん:復元というものは、基本的には画が中心で、音はそれにあわせていく感じになりますが、今回は戦争に関するセリフが削られていたこともあり、画と音を同じぐらいの重要さをもって復元に挑んだという意識があります。音を優先して復元した部分もあります。つまり音はあるけれど画の情報がなく、黒コマになった部分が0.5秒ほどありましたが、その0.5秒の音を生かすために、前後から似たような画をもってきてつないだこともありました。なるべく小津さんが作ったであろう、セリフだとか、カットのリズムだとか、編集のテンポだとか、そういったものを、音的な要素を非常に重要視して復元したことが特徴です。
市山PD:また、今回、新しいバージョンを見てもう一つ思ったことがあります。セリフは全て聞き取れるのですが、多少ノイズは残っていますよね。デジタル修復というとノイズを全部取って、クリアにするべきじゃないかという人もいるかもしれませんが、僕は多少ノイズが残っている感じが、実はリアルなんじゃないかと思いながら観ていたのですが。そこは意識されたのですか?
大澤さん:そうですね。復元というとピカピカにきれいにするというイメージがあるかと思いますが、国立アーカイブにとっての復元とは少し違いまして、その映画のオリジナルが最初に公開されたその状態に戻すことを復元と考えています。ですから、当時の映画館ではノイズがあろうということです。それを聞いていただろう観客の体験を尊重するというか、重視して、それも歴史というとらえ方です。
市山PD:確かに、デジタル修復が始まった頃、ヨーロッパの映画を観るとものすごくクリアに聞こえていて、公開当時にはこんなにクリアではないのではと思ったことがありましたが、海外でも最近はそのあたりも考えているのでしょうか?
大澤さん:今はわりと猫も杓子もデジタルリマスターという風潮があるので、誰が復元にあたったかとか、誰が監修したかによって多分大きく変わるのだと思います。
市山PD:小津のデジタル修復版もたくさんありますし、ほかの映画もたくさんありますけれど、単に修復しましたってものと、緻密な作業でやったものとではかなり違いますか?
大澤さん:そうですね。もちろんノイズを一切なくそうと思えばできるかもしれないけれど、それによってセリフの質、音響的な質も変わりますし、セリフと背景の音、サウンドエフェクト的な音とのバランスも変わるので、気になる音を消せばいいっていうものでもないと思いますね。
市山PD:作業はどのぐらいかかりましたか?
大澤さん:これは、イマジカさんと松竹さんがすごく急いでくださりまして、通常よりかなり特急で、3~4か月ぐらいで作業していただいたと思います
市山PD:本来ならばもっと時間がかかるわけですね。
大澤さん:そうです。
市山PD:また、復元の話とは別の話なのですが、今年、神奈川近代文学館で小津安二郎展が開催されまして、戦時中の、従軍された時の経験など、かなり詳しい当時の日記や手紙が展示されていて、とても新しい発見がありました。この作品は、そういう意味では戦時中で、従軍から帰ってきた後なので、そうした影響があるような気がするのですが、その点ではどのようにお考えですか?
大澤さん:脚本は昭和12年(1937年)、小津のフィルモグラフィーでは『淑女は何を忘れたか』(1937)の頃に既に書かれていたものです。ただ、その脚本と5年後に作られた脚本では、とても似ているんですが、決定的に違う点があります。それは、戦争に関するものが最初に書かれた脚本には一切ありません。そもそも父と息子が会えないのは、息子の就職難で会えないという物語になっています。また、謝恩会で歌った歌は校歌になっています。
それが映画では、父と息子はなかなか会えないけれど、兵隊検査があるのでその時に会えるとか、謝恩会で笠 智衆が祝詞を聞いているとか、ところどころ戦争に関する言及が挟み込まれています。
今日観ていて気付いたのは、平田先生(坂本武)の生意気な息子・せいちゃんがニュース映画を見に行くために、姉・光子に映画代金を要求する場面です。当時ニュース映画は大人気でした。当時はテレビがないため、戦争に関する報道、戦地の様子を映像で伝える手段がニュース映画しかなかったんですね。それでニュース映画の専門家が出てくることもあり、当時大人気でした。なぜ子どもがわざわざニュース映画を観に行くのかというと、そういう背景があるからです。
ところどころにそうした戦争の影響を感じます。物語自体は基本、父と息子の2人しか登場人物がいないような純粋な物語で、父と子のお互いのことが好きで好きでたまらなくて、最初から最後まで相思相愛がずっと続きます。その2人の物語に外から枠をはめるというか、社会的に枷をはめる形で当時の社会状況としての戦争が描かれていて、笠 智衆はまさに社会のために息子をちゃんと育てるということを己の使命にしています。学校の先生をやっていたので、生徒たちも同じ息子といえるわけですよね。ただ、冒頭で事故を起こして、そのたくさんの生徒を育てることには一回挫折して、それを取り戻すかのように今度は自分の子ども(佐野周二)を育てることを使命とする。だから本当はお互い一緒に暮らしたいし仲良くしたいんだけれども、社会的な使命があるからところどころで2人は一緒にいられないという、メロドラマの動機というかあやを付ける物として戦争が非常に強い装置として使われているなと思います。
笠 智衆によるキャラクターの強さも、戦争という、肩に乗っている社会的な責任の重さに応じて厳格なキャラクターはできていると思います。この前の作品の『戸田家の兄弟(1941)』でも次男の佐分利信がこれまでの小津作品にあまりなかったような強いキャラクターで、現在残っているバージョンにはありませんが、本来は終盤に自分の兄弟を平手打ちする場面が撮られているはずです。小津自身の戦地の体験で、暴力を見てきて、仲間が死んでいって。田坂監督の『五人の斥候兵(1938)』を戦地で観るものの、自分の考えるリアリズムとは違うとまで言っています。やはり戦争と映画に対する認識を大きく変えたはずです。笠 智衆や『戸田家の兄弟(1941)』の佐分利信のキャラクター像、暴力的な決然とした男性キャラクターは、そういったことと何か関係があるのではとつい考えてしまいます。
市山PD:『戸田家の兄弟(1941)』の殴る場面がなくなったというのはやはりGHQの検閲?
大澤さん:そうですね。これも同様に、フッテージが残っていれば作品の観方をまたガラッと変えるような場面だったと思います。何とか見つけたいですね。
市山PD:東京国際映画祭ではデジタル修復されているものを、国立映画アーカイブではデジタル修復されていないもの、つまりまだ35ミリ版で残っているものを上映しています。『戸田家の兄弟(1941)』もこれから上映の予定があるので、ぜひそちらも観ていただきたいです。
最後に一言お願いします。
大澤さん:いたるところで小津上映がやっています。ぜひ小津にどっぷりと浸かってください。