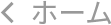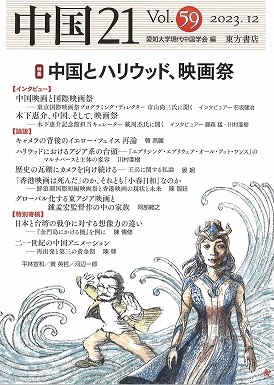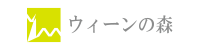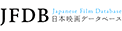『東京画』から40年。東京の変化を見つめ続けるヴィム・ヴェンダースに聞く 東京国際映画祭と新作『PERFECT DAYS』

ヴィム・ヴェンダース監督
撮影/間庭裕基
撮影/間庭裕基
第36回東京国際映画祭審査委員長を務める、ドイツのヴィム・ヴェンダース監督が10月23日に来日した。小津安二郎監督作品への造詣が深く、1983年には東京の街と小津監督の足跡をたどるドキュメンタリー『東京画』(85年製作、日本公開は89年)を撮影した。ヨーロッパの映画監督で、もっとも東京とゆかりの深い監督のひとりと言っても過言ではないだろう。映画祭会期中の10月26日、ヴェンダース監督に話を聞いた。
――あなたが『東京画』でも映した日比谷地区で今年の東京国際映画祭が開催されることをうれしく思うとともに、『東京画』を見ることによって、私(筆者)が知らない時代の東京を教えてもらったようでした。
小津安二郎監督の作品も同様でしょう。『東京画』は1983年の4月に撮影しました。和光やJRの線路、皇居は今もそのままですが、街は大きく変わり、私が「東京画」で映したランドマーク的な建物はなくなってしまったようですね。当時の東京は私にとってSFの世界のようにモダンな場所でした。今、振り返るとあれも古い東京になってしまったのでしょう。
――『東京画』撮影当時は、日本の経済状況が良い時代でしたが、現在は東京と東京に住む人々の暮らしも変化しています。今回、東京で日本人キャストともに日本語の劇映画『PERFECT DAYS』を作られました。渋谷区の公園のデザイナーズトイレ清掃の仕事に従事する、下町の古いアパートにひとりで住むシニア男性が主人公です。
東京には頻繁に来ているので、時代によるアップダウンを私も感じ、生活のスタンダードが変わってきていると思います。しかし、日本の皆さんはそういった変化も柔軟に対応されているのではないでしょうか。
私にとって、『PERFECT DAYS』を作ったのは自然なことでした。これまで多くの日本の方々とお話をして、1983年に『東京画』を撮った時には、カメラマンの厚田雄春さんと長く話しました。もちろん通訳さんを通してですが、日本語の音がとても私の耳になじんで、美しく聞こえるのです。日本語の意味が分からなくても、何を伝えようとしているのかが、よくわかるのです。厚田さんが、涙を浮かべて小津監督が亡くなった悲しみを語ること、カメラマンとしての人生が終わったと伝えることが、手に取るようにわかりました。
昨年の5月に一度東京に来ました。東京のロックダウンが終わって、人々が日常生活を取り戻しつつあることを喜びをもって迎え入れる雰囲気を目の当たりにし、それはヨーロッパでのロックダウン後の社会と全く異なることに驚いたのです。とりわけ私の住む地域では、喜びではなく、社会性を失ってしまった感じでした。公園は2週間でゴミだらけになってしまって、それを片付けるのにまた長い時間がかかるような有様でした。日本は真逆で、ステイホームの生活から自由を取り戻し、公園、公共施設を大事にしようという気持ちをお持ちだったと思います。それで秋にまた東京に戻って、この映画を作ろうと決意したのです。
――『PERFECT DAYS』も、あなたの過去の様々な作品からも、街、都市への独自のまなざしが感じられます。渋谷の公園以外に、主人公の平山さんの住む下町の地域も、ご自身がロケハンで回られたのですか?
私は自分が撮影する場所に共感を持てないと、撮影がスムーズに進まないのです。ロケハンは常に自分が行くようにしています。平山さんが住む場所として、押上はぴったりでした。墨田川が流れ、浅草があって……古き良き東京を象徴していて、あたかも平山さん自身のような街。オールドファッションな彼が、首都高を通ってモダンな渋谷に行く。その距離感も最適だと思ったのです。
――東京をよく知るヨーロッパの映画監督のひとりであるヴェンダース監督に、今回東京国際映画祭で審査委員長を務めていただくとことは、日本の映画ファンにとって非常に光栄なことです。コンペティション作品の審査はどのように進めるのでしょうか?
慣例として映画祭の最後に審査委員会議を開くものですが、私はそれでは十分ではないと思い、期間中の中盤にも一度、深い話し合いの場を持つことにしました。そうでなければ十分な審査はできないだろうと私が提案したのです。コンペティション出品作を見るのは審査委員皆一緒なのですが、それぞれの好みもあるので、座る席は全く別々になります。私はメモを取るタイプなので、ほかの方の邪魔にならないような場所に座ります。
――東京国際映画祭では『PERFECT DAYS』と同時に、田中泯主演の短編『Some Body Comes Into the Light』、そしてあなたの母国である戦後のドイツを代表するアーティスト、アンゼルム・キーファーを映した3Dドキュメント『アンゼルム』も上映されます。キーファーは快く撮影を許可してくださったのでしょうか。
もちろん彼はとても神経質になっていました。制作中の場面は私とアシスタントとカメラマンという最小限の人間のみで臨みました。ただ、彼は私の旧知の友人で、信頼関係があるので、彼の制作時以外の場面はしっかりとした体制のクルーで撮影できました。
――あなたが敬愛する小津安二郎の映画を再発見できる特別企画もあります。小津作品に親しみのない日本の若い世代に薦める作品を教えてください。
上映とともにシンポジウム(10月27日に終了)も開かれる『お早よう』(59)が良いかもしれません。小津作品にしては珍しいコメディですし、子どもたちが主人公ですから見やすいと思います。また、日本の庶民の文化の過渡期を描いています。テレビを家に持つということがテーマで、この作品の子どもたちはテレビを欲しがります。今ではインターネットなのかもしれません。それがコミカルに描かれているので、楽しく見られると思います。
――『お早よう』ではテレビで人々が皆同じ番組を見る時代でしたが、今はスマホやストリーミングの登場で、テレビ番組や映画の鑑賞スタイルが細分化されました。
パンデミックで映画の将来が一変したと思います。残念なことに劇場が閉まって、多くの人々にストリーミングで見る癖がついて、新しい作品もすぐに自宅で見られるようになり、劇場には足を運ばなくなったと思います。パンデミックの期間、幼い一つの世代が映画館で映画を見るという経験をせず年を重ねたので、そういった層が映画館に来なくなることは残念です。
――東京国際映画祭は、ヴェンダース監督が常連のカンヌ、ベネチア、ベルリンなどはもちろん、お隣韓国の釜山国際映画祭などに比べてもまだまだ世界的な知名度や発信力が高くはないと思います。今後の東京国際映画祭に期待すること、アドバイスはありますか?
映画祭は上映される作品で評価されます。つまり、上映作品が良ければ、それは良い映画祭で、評価は何よりも上映させる作品いかんだと私は思います。ベネチアはやや評価が低くなった時期もありましたが、最近になって随分盛り返したと思います。それは、例えばどういう作品を上映できるか? また、どういったプレゼンテーションをするかということです。例えば、ベネチア国際映画祭では早くからNetflix作品を上映しましたが、しばらくカンヌはしていませんでした。どちらが正しい選択かはわかりませんが、それぞれの映画祭が自分たちの評価を勝ち取らなければいけません。そういった部分では東京国際映画祭にも頑張ってほしいです。一つ言えることは、私が今まで経験した中で、今回の東京国際映画祭のレッドカーペットが一番ユニークでした。まわり道のように、くねくねと曲がったレッドカーペットを私は楽しみましたよ。
第36回東京国際映画祭は、11月1日まで開催される。
新着ニュース