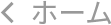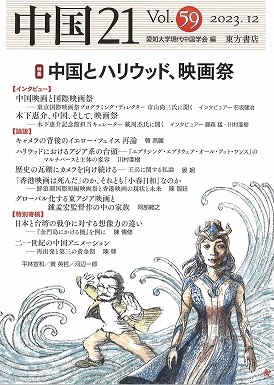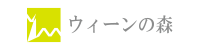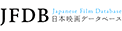ドイツの人気小説の映画化に突き動かされた女性2人の熱意、原作者も巻き込む

第36回東京国際映画祭のコンペティション部門に選出されたバルバラ・アルベルト監督の最新作『真昼の女』が10月24日、東京・TOHOシネマズシャンテで上映された。アルベルト監督は、脚本のメイケ・ホーク、作曲のキャン・バヤニ、俳優のマックス・フォン・デア・グレーベン、プロデューサーのオリバー・シュンドラーと共にQ&Aに出席し、観客からの質問に答えた。
本作は、ドイツの作家ユリア・フランクの小説の映画化。医学を志して地方からベルリンに出てきたユダヤ人女性ヘレーネ(マーラ・エムデ)が、ふたつの世界大戦という激動の時代のなかで、従軍看護師として、母として、妻として、ひとりの人間として生き方を模索する姿を描いた女性の一代記だ。
なぜ『真昼の女』を映画化しようと思ったのか、企画の始まり、原作小説との出合いについて脚本のホークが語る。
「原作は、2007年にThe German Book Prizeを受賞しているドイツでは人気の小説です(日本でも「真昼の女」のタイトルで出版されている)。読んだとき、感動したのはもちろん、何としても映画化しなければ! と突き動かされるものがありました。普遍的なテーマが宿っている物語であると。映画化するために監督のバルバラさんに声をかけたことが企画の始まりでした」
アルベルト監督と脚本のホークは、大学で一緒に働いていた時期もあったという。そして、彼女たちの熱意に動かされ原作者のユリア・フランクも加わり、3人の意見を反映させながらホークは脚本を書き上げていった。
監督・脚本家・原作者、3人の女性たちによって仕上げられた脚本について、プロデューサーのシュンドラーは、現代にも通じるメッセージが込められていると話す。
「この映画の撮影が開始されたとき、世界ではロシアとウクライナの戦争が勃発しました。最近もまた別の戦争(パレスチナとイスラエルの戦争)が勃発しています。昔も今も、歴史上の事件や戦争は、女性の希望や幸せ、人生における計画、職業における歩みを阻んでしまいます。そういったこともこの映画で描いているのです」
観客からも「脚本がとても素晴らしかった」という熱い感想があり、そのなかで特に素晴らしいと感じたエンディングの質問について、アルベルト監督は「小説と映画のエンディングは異なる」と映画に込めた想いを語る。
「希望の兆しが感じられるようなエンディングにしたいと思い、映画では原作とは異なる結末を用意しました。主人公ヘレーネも彼女の息子もそれぞれ罪悪感や痛みを抱えて生きています。過去を乗り越えられないにしても、乗り越えようとする2人を描きたかった。争いがはびこる世の中に向けて、和解への努力、そして希望を伝えたいと思ったのです」
また、主人公ヘレーネはある種のアイデンティティ・クライシス(自己喪失)を抱えているように感じたという意見もあり、そういった内面の葛藤を映像として描く難しさについて、アルベルト監督は「アイデンティティについて言及すると、この映画のもうひとつの主題は、女性の肉体であると思っています」と説明する。
「俳優にとってセックスシーンはとても大変だったと思いますが、ヘレーネを演じたマーラさんも(登壇者のマックス・フォン・デア・グレーベンさんも)徹底的に準備をして、自身の肉体を使って、本当に素晴らしく演じてくれました。振り付けをして、俳優も撮影監督もまるでダンスを踊るかのように演じて撮っています。いろいろなセックスシーンがありますが、それぞれのシーンに意味があるのです」と、俳優とスタッフを評した。
第36回東京国際映画祭は、11月1日まで開催。
新着ニュース