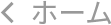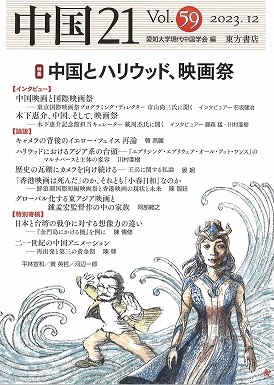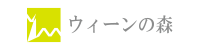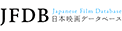『鳥たちへの説教』監督、字幕版を作る際に「どこか間違えて」とリクエストする理由

ヒラル・バイダロフ監督
第36回東京国際映画祭のコンペティション部門に選出されたヒラル・バイダロフ監督の最新作『鳥たちへの説教』が10月24日、東京・TOHOシネマズシャンテで上映され、バイダロフ監督がQ&Aに出席し、観客からの質問に答えた。
本作は、『クレーン・ランタン』(21)で東京国際映画祭芸術貢献賞を受賞したバイダロフ監督の最新作。アゼルバイジャンの森を舞台に、戦争が人々に残した傷がもたらすドラマを驚異的に美しい映像で描く。バイダロフ監督は脚本、編集、撮影、プロデューサーも兼ねた。
初来日だというバイダロフ監督だが、「日本の文化、映画、絵画もすべて愛しています」とにっこり。「日本のクラシック映画のほぼすべてを観ています。今まで日本についてとても多くのものを観てきました。世界中には日本文化の中毒の人が多くいると思いますが、私もその一人です」と日本への愛を口にした。
本作に臨んだきっかけについて、バイダロフ監督は『クレーン・ランタン』を作った時に、とても辛い思いをした。2年間かけてあらゆる場所、いろいろな気候の中で撮影をしました。台本を書かずに、自分で何を撮っているのかわからないまま撮り続けて、編集をしながら映画を完成させました。完成させた後には疲れ切ってしまいました」と苦笑いを浮かべる。
それでも「ただ常に、私の中で何かを作りたいという意欲があります。疲れ切った体を休めようと木の下に座っていた時に、夢のような作品を作ろうとひらめいた」と疲弊しながらも、創作意欲が湧いたと回想。「子どもの頃に聞いた戦争に関する物語を題材に、夢のような音楽が流れる作品にしようと決めて作り上げた」と話す。
観客から「とてもポエティックで、やや難解な印象を受ける映画でもあります。そういったスタイルを貫く理由は?」との質問が上がると、バイダロフ監督は「本作を母国語で観ても、多くの人にとって、この作品のセリフを理解することは難しいんです。『クレーン・ランタン』もそうでした。文法も間違っているし、流れもつながっていないので、なかなか理解することは難しい」と切り出し、「ただ僕は内側に湧いてくる言葉を書き留めていると、それが自分では止められない。映画には独自の言語があると思っています。それはコミュニケーションをするためでもなく、皆さんに美しい文章を伝えるためでもありません。内に湧いてくる言葉を書き留めて、それをひたすら映像化しているということになります」と持論を展開。
続けて「今回は字幕版で観ていただいていますが、字幕を作ってもらう時にいつもお願いすることがあって。「どこか間違えてほしい。少し理解しにくいようにしてほしい」とお願いしています。ロジックとしてはわからないけれど、何かを感じ取ることができるような映画。私自身、そういう作品を目指しています。僕の中にある内面の声を聞いてもらうために、映画を作っています」と穏やかな表情ながら、映画づくりへの情熱をあふれさせていた。
また「鳥や木、壁、窓、カメラのレンズもすべて本作の登場人物だと思っています。エンドクレジットにも、役者やスタッフだけではなく、そういった細かいものもすべて入れたいくらい」と人間だけではなく、そこに存在するすべてが登場人物だと語ったバイダロフ監督。「本作の撮影は5人の小さなグループで行いました。毎日、撮影用の機材を山の下の村から担いで、3時間かけて頂上に運んでいました。そういった時間も、作品の一部として大切な要素になっています」とチームへの信頼感と共に、映画に込めた思いを明かしていた。
第36回東京国際映画祭は、11月1日まで開催。
新着ニュース