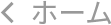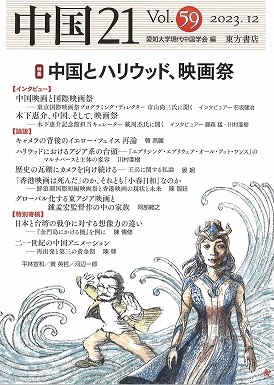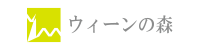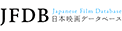開催までいよいよ1ヶ月を切った9月27日(水)に東京日比谷ミッドタウンBASE Q HALLにて第36回東京国際映画祭のラインナップ発表記者会見が開催。ゲストとして、フェスティバル・ナビゲーターの安藤桃子監督とコンペティション作品より小辻陽平監督、富名哲也監督が登壇しました。

今年の映画祭は、10月23日から11月1日の10日間、昨年に引き続き日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区にて開催。また、昨年同様にオープニングのレッドカーペットを日比谷仲通りにて開催予定。また4年ぶりのフィジカル開催となる映画祭併設のマーケットTIFFCOMは、10月25日から27日の3日間の同時期開催。今年は、総勢約600人以上の海外ゲストが招へい予定であり、コロナ禍では積極的に実施が行えなかった「交流ラウンジ」などの映画人の交流の場を充実させ、世界中の映画人とファンとの交流が活性化していく年となります。
東京国際映画祭チェアマン安藤裕康による開催の挨拶で会見は始まり、本年度の映画祭の特色として「今年の映画祭といたしましてはコロナ禍を乗り越えて、さらなる飛躍をしたいと目指しております。作品の質・量ともにグレードアップしていく必要があると考えており、作品数は219本(昨年は174本)と約25%増えております。国際交流を大いに強化したいと考えて、海外からもたくさんのゲスト(現時点で600人以上)に来ていただき、日本の映画人や一般の方と交流していただくということを目指したいと思っております。さらに大いに祝祭感を盛り上げたく、関連イベントでは小津安二郎監督の誕生120周年ということで様々なイベントを実施し、小津監督のほぼ全作に近い35本を上映いたします。また今後の方向性として、アジアの国々との連携を強化してアジアの映画祭としての特色をより鮮明に出していきたいと思っております。今回上映する作品の6割以上がアジアの作品であり、お呼びするゲストの半分以上の方々がアジアからいらっしゃいます。昨年に比べ協賛会社が11社増え、例年以上に盛り沢山な企画を揃えることができました。以上を持って我々は映画祭を実施いたしますが、皆様方のご支援をよろしくお願いいたします。」と発表しました。
続けて、本年の審査委員長であり『パリ、テキサス』(84)『ベルリン・天使の詩(うた)』(87)など多くの映画祭受賞作を手がけ、最新作の『PERFECT DAYS』ではカンヌ国際映画祭にて主演の役所広司が最優秀男優賞を受賞、東京国際映画祭は2011年の第24回以来4回目の参加となるヴィム・ヴェンダース監督より「東京国際映画祭にまた戻ってこられることを嬉しく思います。今年の東京国際映画祭は私が敬愛する巨匠・小津安二郎監督の死後60年、生誕120年の 記念すべき年に開催されるもので、そんな機会に参加できることは私にとっては特別なことです。」とコメントが紹介されました。
また、昨年まで俳優・女優が歴任してきた「アンバサダー」を、映画祭をより楽しんでもらうための案内人である「ナビゲーター」という肩書きに名を変え、同ナビゲーターに就任した安藤桃子監督が登場。安藤監督は「今年から「アンバサダー」から「ナビゲーター」という肩書きに変わったのが、すごく大きな東京国際映画祭の指針にも感じられました。これから先、私たちがどこに向かっていきたいかという道を示していくことが、“ナビゲーション“だと思っていますので、東京国際映画祭もそういったことを意識されたんじゃないかなと感じて、ぶっ飛ぶほどに光栄に感じました。」と任命された想いを語った。

その後、プログラミング・ディレクターの市山尚三より「コンペティション部門」15作品の紹介に続き、「コンペティション部門」に選ばれた日本映画3作品が発表し、『曖昧な楽園』の小辻陽平監督、『わたくしどもは。』の富名哲也監督が登場。小辻監督は「この作品のきっかけになったのは、私の祖父が亡くなった時の最後の時間をもとにして映画を作りました。曖昧で漠然とした瞬間を写したいと考え、実際の人生に近いような複雑であったり、漠然とした感覚に近い映画になれたならと思って作りました。」と語りました。

富名監督は「今回の『わたくしどもは。』という作品は新潟県の佐渡島で撮ったのですが、1作目『Blue Wind Blows』(18)も佐渡島で撮っており、メイン舞台の佐渡金山という場所を初めて訪れた時、その場所から得たインスピレーションを受けたものを映画にしました。」と作品に込めた想いを語っていただきました。
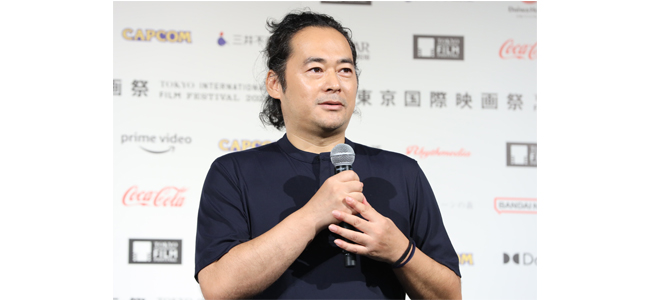
また同部門には岸 善幸監督作『正欲』も選出されています(記者会見にはスケジュールの都合で不参加。)
※コンペティション部門選出の日本映画3作品は、27日~29日まで受付の先行抽選販売の対象となっております。
先行抽選販売の申込みは →コチラ
その後、石坂健治シニア・プログラマーより「アジアの未来」部門の作品の紹介。市山プログラミング・ディレクターによる「ガラ・セレクション部門」作品と今年生誕120年になる小津安二郎特集をはじめとした様々な特集を紹介。続けて、藤津亮太「アニメーション」部門プログラミング・アドバイザーより作品を紹介。「アニメーション」部門では今年からコンセプトを一新し国内だけにとどまらず海外の話題作からも作品が選出された。さらに司会より今年の新たな取り組みが発表され、国内外の独自で豊かな映画文化を紹介し、刺激や感動と出会い、交流する場である「第1回丸の内映画祭」と、ジェンダー平等、環境、貧困、多様性、差別といった現代の重要な社会テーマに向き合った作品が対象の「エシカル・フィルム賞」、また昨年復活した「黒澤明賞」や「Amazon Prime Videoテイクワン賞」「交流ラウンジ」などのその他の部門の紹介、カンヌ国際映画祭でも実施されている映画界やアート界の様々なポジションで活躍する女性達に光を当てるケリング「ウーマン・イン・モーション」のトークプログラム、ベネチア国際映画祭生涯功労賞受賞の俳優トニー・レオンによる主演作『2046』上映後のマスタークラスなど例年以上の盛り上がりが予測される様々なイベントの紹介がされた後、最後に質疑応答が行われ、会見は終了しました。
第36回東京国際映画祭 上映作品・イベント一覧は →コチラ
【安藤桃子監督 Q&A】
Q.安藤さんは今回ナビゲーターということですが、最初聞いたときはどうでしたか?
安藤桃子監督:今年から「アンバサダー」から「ナビゲーター」という肩書きに変わったのが、すごく大きな東京国際映画祭の指針にも感じられました。コロナがあって世界中から映画監督やゲストをお迎えすることができなくなったという現実がありましたが、それを得てこれから先、私たちがどこに向かっていきたいかという道を示していくことが、”ナビゲーション”だと思っていますので、東京国際映画祭もそういったことを意識されたんじゃないかなと感じて、ぶっ飛ぶほどに光栄に感じましたし、同時に色々と考えました。
Q.安藤さんの東京国際映画祭へのイメージってどんな感じでしたか?
私自身の作品も出品させていただいた経験もありますし、昨年は実はこっそりと…移住先の高知で小さいながらも映画祭をやりたいなという思で視察に来てみたりとか。いっぱい学ばせていただくこともあり、東京という日本の中でも世界中から中心として人々が集まる場所で、国際映画祭を代表する映画祭が行われることが、私の中でもずっと大切に注目してきている映画祭でもございますので嬉しいです。
Q.安藤さんはご自身で高知の映画館の代表も務めていたりしますが、安藤さんにとって映画とはどんな存在でしょうか?
例えばアートでよく言われるのですけれども、アートはアートにあるのでなく見る人の心の中にアートがあると。どう感じるか、心の中にアートがあるというのは映画も同じだと思っています。映写機と触れ合っていたりすると、電球が照らしてくれるスクリーンがあって、私たち見る一人一人の中に映画があるというのは確実だと思います。映画は我々の未来や、一人一人の人生を導いてくれるようなメディアだと思っております。
Q.今年の映画祭でやってみたいことなどありますか?
一番は、映画祭に本当に数年ぶりに各国から、世界中からいらっしゃるゲストと出会って、”今”の世の中のこと、これから先私たちがどんな道に向かいたいかを、是非とも直接肌で語り合いたいなと思っております。
【小辻陽平監督、富名哲也監督 Q&A】
Q.監督にとって東京国際映画祭はどんな存在でしたか?
小辻監督:実は僕は、東京国際映画祭に参加できたことはなかったのですが、毎年プログラムはチェックさせていただいておりまして、国内・海外の素晴らしい映画たちが集まった日本を代表する映画祭だと認識しております。まさか自分がこの場に出るとは思っていなかった、それくらい雲の上の存在というふうに考えておりました。
富名監督:私も東京国際映画祭は、はじめての参加になります。今回が2本目の作品なのですけれども、以前はラブ・ディアス監督などの上映作品を観ることはあったのですが、映画祭への参加は今年が初めてなので、とても楽しみにしております。
Q.東京国際映画祭のコンペに選ばれた作品について、どういう趣旨で作品を作られましたか?
小辻監督:この作品のきっかけになったのは、私の祖父が亡くなった時の最後の時間をもとにして映画を作りました。曖昧で漠然とした瞬間を移したいと考え、実際の人生に近いような、複雑であったり、漠然とした感覚に近い映画になれたならと思って作りました。
富名監督:今回の『わたくしどもは。』という作品は新潟県の佐渡島で撮ったのですが、1作目『Blue Wind Blows』(18)も佐渡島で撮っており、メイン舞台の佐渡金山という場所を初めて訪れた時、その場所から得たインスピレーションを受けたものを映画にしました。
Q.映画祭で何かしたいことはありますか?
小辻監督:この作品はスタッフ、俳優全員の力とアイディアで作れた映画でして、決して僕が全てコントロールして作った映画ではないんですね。俳優陣とは作成の直前まで対話だったりリハーサルだったりをしながら映画を広げていきましたし、本当に小さなチームで作ったのですけれども、本当に素晴らしい俳優・スタッフが関わってくれましたので、この東京国際映画祭という大きな舞台で彼らのことをより多くの方に知っていただけたらなと思っております。
富名監督:私も同じような感じで、夫婦で作った作品で本当に小さな作品なんですね。撮影期間もすごく短く、コロナの中でスタッフや豪華俳優陣の方々に参加していただいた作品なので、この機会でワールドプレミアを迎えられたので、みんなに見てもらえたらなと思います。
【安藤監督、小辻監督、富名監督への質疑応答】
Q.今回の東京国際映画祭で観たい映画はありますか?
安藤監督:ユースの作品です。今の若い方々が、どういう視点で切り取っているかというのが、子供たちの映画制作のワークショップもさせていただいているので、すごく興味があります。
小辻監督:僕は『彼方のうた』を拝見するのをとても楽しみにしています。前作の『春原さんのうた』(21)を拝見して、とてもすごく感動しましたので最新作をとても楽しみにしております。
富名監督:小津監督の特集上映を楽しみにしております。観たことない作品が多くあるのでそれを是非観たいです。
Q.富名監督へ、2作目も佐渡で撮ろうとしたきっかけと、ロケ地での思い出や作中にどのように佐渡風景を落とし込んでいったか?
富名監督:きっかけは1作目の撮影が終わって、佐渡金山の近くを通って何か引っ張られるような感じがして訪れた時に、ちょっとした歴史を知って、江戸時代の金山だけじゃない地元の人たちの生活だったりを勉強して知って、なんとか映画にしてみたいとおもいました。風景に関しては、佐渡の風景が素晴らしいので、そこにあったものを絵に落とさせていただきました。
Q.監督のみなさんは映画の世界でこれからどういう風に向かっていきたいとお考えですか?
安藤監督:技術的にはこれからどんどん思いもよらない撮影技法とか発展進化していくと思うんですけれども、上映の仕方もスマホでも観られる、どこにいても映画が観られる時代で、だからこそ変わらない本質というのがより一層際立ってくるんじゃないかなと思ってます。今回東京国際映画祭で、まだ観ていない初めて私たち日本人が目にする作品も多々あると思いますが、そこに集う映画という言語の本環にある視点だと思います。その世界中の方々の視点というものは、全く変わらないと思うので映画界の未来というのはもっと原点回帰していく=心というところに基づいてくるんじゃないかなと思っています。
小辻監督:自分自身にとっては映画作りって勝手にやっている自由研究のようなものでして、今作は自主制作という形で作りまして、前作の短編『岸辺の部屋』(17)の経験を経て今作を作りました。また今作を経て何年かしてまた自分なりの映画というのを作っていく、そんな形かなと思っております。
富名監督:今作はインディペンデントで作った作品で、映画は難しくて同時に怖いなと思っておりまして、撮ろうと思ったら何でも撮れるとは思うんですけれども、歴史があるので簡単に撮りましたとは言えないような思いはある芸術だなと思っております
Q.安藤監督へ、映画祭のビジュアルにも登場されているお父さま(奥田瑛二)ですが、今回映画祭に2人でどのように参加したいか、今後なにかでご一緒に活動される可能性はありますか?
安藤監督:実はもうあったりして…笑。それは映画祭とは別なんですけれども、タイミングとして父から受け継いでいくことも父自身も意識する年齢となり、俳優としても長年映画界に身を置いてきた父の姿を見ていて、そこで私もたくさん出会わせていただいた今は亡き監督や先人、先輩の方々の想いや志してきたこと、それからこれから先どのいう映画界にしていって欲しいかというメッセージを、今回ビジュアルを撮影させていただく中で、2人で並びながら見えないバトンがつながっていく気持ちで、大変光栄で胸がいっぱいになるような想いを持ちながら景色の中に立たせていただきました。
【安藤裕康チェアマン、市山尚三プログラミング・ディレクター Q&A】
Q.近年、映画業界での性暴力・性加害の問題がありますが、東京国際映画祭としてのハラスメントに対する対応や声明などをお持ちであればお聞きしたいです。
安藤チェアマン:性加害の問題や人権の問題などについては、非常にセンシティブに真剣に向き合っていき、人権を侵すようなことは断固として許されるべきではないと考えております。映画に出演する方の活動の場を失うようなことにはなってはいけないとは思っておりまして、いずれにしましても本件は社会でも調査は続いておりまして、それに対する対処の仕方についても社会全体として各方面で議論し処置が行われている最中でございますので、私たちとしても非常に、真剣に注視していきたいと思っております。
Q.映画祭でのジェンダーバランスについてお聞きしたいです。
安藤チェアマン:ジェンダーについても大変真剣に考えておりまして、国際的に映画祭の中における男女のバランスにおける問題に真剣に向き合う運動がございまして、我々はそれにアジアで初めて署名をいたしました。それから今年の傾向について、全部門での女性監督、男性監督の割合というのは男性77%、女性21%(その他2%)と男性の方が多くはなっておりますが、常にジェンダーバランスを意識しながら映画祭としては作品本意で選定を行なっておりますので、割合のバランスを注意を払っていきたいと考えております。映画祭に携わるスタッフについては、意識的にできることが多いので女性の割合を多くする配慮を行っております。(今年度の割合は男性37%、女性62%)また、コンペティション部門審査委員についてはジェンダーバランスが5:5になるように、そのほか各部門に関しても女性に入っていただくように配慮をしております。我々はこういった取り組みを通じて、ジェンダーバランスについてを常に注意を払っていきたいと思っております。
Q.手元で映画を観ることができる現代、改めて映画祭を開催する意味はなんでしょうか?
市山PD:基本的に映画は一人で観て完結するものではなく、集団で観てみた映画がどうだったかをそこで話したり、孤独に観るだけではなくそこから広がっていくメデイアであると思っております。それが世界中で映画祭が開かれる大きな理由の一つだと思っており、配信などで観ることもでき、SNSでも情報を発信することもできる世の中で、映画祭がなくても良いという考え方がこれから出てくるかもしれません。ただ、そこで多くの人が集まって監督であったり、主演の俳優であったり、関係者であったりの話を聞くということは、インターネットが発達しなくなるだろうと言われていても、全くなくなっておらず、映画祭には何か人を集める力、集まっていくことで活性化していくなにかがあると思います。ただ映画を観せるだけではなく、そこに人が集まるというのを映画祭は積極的に作らないといけないと我々は考えております。映画学校やマーケットなど映画を観ること以外でも映画祭を維持していくことが重要な課題になってくると思います。
「コンペティション部門」 応募作品数()内は昨年数:1,942本(1,695本)
国と地域数:114(107)
全体の上映本数:219本(174本)
そのうちの女性監督作品の比率:20.6%(23.2%)