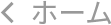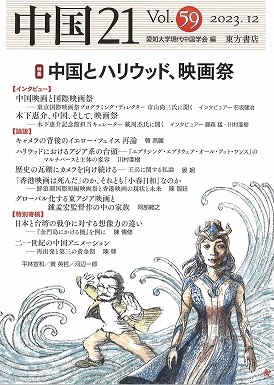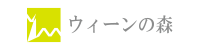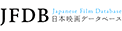東京国際映画祭公式インタビュー:
コンペティション
『ロングショット』
ガオ・ポン(監督/脚本)

今ある世界は、90年代に起きた世界経済の変容によって成り立っている。当時の最大の変化は、「世界の工場」となった中国だろう。だが、改革開放政策によって現地で起きていたことは、あまり知られていない。その一端を劇映画化したのが『ロングショット』。国際大会でも活躍した射撃選手のシュエビンは、右耳の聴力を失い鉄工所の警備部へ。給料を払えないことでほぼ開店閉業状態の工場では、夜な夜な盗難が繰り返されており、シュエビンは盗難犯と工場上層部との癒着に気づく。
世界の工場になる直前に起きていた中国東北部の第2次産業の斜陽化、恵まれた環境にあったナショナルチームの元アスリートですら社会から転げ落ちるという現実……。ガオ・ポン監督は、激変の90年代に起きた事実を織り交ぜながら、長編第一作にして重厚なドラマを築き上げた。
――長編デビューおめでとうございます。北京電影学院を卒業されて15、6年、長編を撮るまでにかかってらっしゃいますね。まずは、それまでのキャリアを聞かせてください。
ガオ・ポン監督(以下、ガオ監督):電影学院を卒業してからテレビ映画の助監督の助監督、アシスタントのアシスタントみたいなことから始めて、初歩からキャリアを始めました。じつは電影学院を卒業した時は、映画監督になるつもりはなかったんです。映画はあまりにも難しすぎるし、CMのディレクターになる方がより現実的な選択だという風に思っていました。
卒業時は、中国のCM業界が発展の可能性を持った活気のある時代。とても有名なCMの監督がいたので、私にとっても憧れの存在だったんです。だから、テレビ業界の後は、CM監督として仕事をするようになり、10年以上CMを作ってきました。憧れの仕事ができていたけど、どこか不満があったんですね。
――不満というと?
ガオ監督:憧れの業界を選んだけど、なんか違う。結局、自分の性格が合わなかったことに気づいたんですね。CM業界で生き抜くためには、ある程度、人に合わせてやるっていうことが必要で。自分を表現することよりは、人のためにサービスをするっていうことの方がCM業界では求められますから。自分の性格は、非常に温厚で大人しい性格なので、そういうことには向いてないんじゃないかという風に思い始めたんです。そういった不満を感じ始めたときから、自分のクリエイションのはけ口として脚本を書き始めたのが、この映画のきっかけになってます。
――不満のはけ口にしては、とても初長編とは思えない出来栄えですよ。では、脚本を書くうえで、なぜ90年代の方に目が向いたんでしょう?
ガオ監督:私の実体験が一番大きな動機です。90年代前半、私は6歳ぐらいだったんですが、ある日両親が家に帰ってきた時、たくさんの紙を持ってきたんです。家の中には置ききれなくて、バルコニーにまで置いていたほどの量です。じつはそれは、康華製紙工場というところで働いていた母親がもらってきた支給品。工場が給料を払えなくなって、給料代わりに紙をくれたんですよ。
――本作の工場のような状況を経験されていたんですね。
ガオ監督:そうです。で、その紙を私は落書き帳や宿題のために使い続けたんです。でも、なかなか使いきれず、小学校から中学校までずっとその紙を使いました。その紙に物語を書いたり、絵を書いたり。10数年かかって使い切るころには、白かった紙が黄色になってました(笑)。

――その思い出をきっかけにリサーチを?
ガオ監督:この映画のために取材をするなかで、90年代初頭っていうのはどういう時代だったのか、いろんなドキュメンタリーとかを観て取材を重ねました。そのうちに、今申し上げた自分自身の家族の記憶が結び付いたんですよ。ちなみに、私の母親がラッキーだったのは、のちのち給料が出るようになったということでした。
――取材を重ねていくと、おそらくご自身の思い出と重なる部分もあれば違うところもあったと思います。
ガオ監督:やはり自分の記憶っていうのは、どうしても主観的なものですからね。今回の東京国際映画祭の開幕作、ヴィム・ヴェンダース監督の『PERFECT DAYS』を拝見したんですが、そこでも気づいたことがあります。あの作品では、夢のパートをモノクロにしていますが、記憶や追憶っていうのは、理性的じゃないものなんだろうな、と共感しました。この映画を撮るために様々な取材をしましたが、それはイコール自分の記憶の裏をとるような作業でもありました。
あの時代の中国は、飛躍的に経済が伸びはじめ、世界の工場になりつつあった反面、とても苦しい痛みを背負い、多くの人がそのために代償を払っていました。時代についていけない多くの人が存在したんですね。うまく時代に適応して乗り切れる人は幸せになれますが、それはごく一部の人。この作品では、社会の大きな変化の中にある人の痛みを表現しようと思うようになったんです。

――90年代はそのネタの宝庫ですね。
ガオ監督:中国においてはそうですね。でも、世界中どこにでもあることでもあります。日本では幕末期を描いた山田洋次監督の『たそがれ清兵衛』でも描かれてますよね。その時代に合わせて生きていけるのか、何が正しいのか、何が間違いなのかっていうことを判断しにくい人たち。時代の変化についていけない人は、どの国にでもいるんですよ。映画芸術を作る私たちにとって、そういった時代の変化を大きな視野で見るということ、それとともに個人の視点をどう描くかっていうことが、とても大事なんだと思ってます。
――他になにかヒントをもらった映画はありました?
ガオ監督:クリント・イーストウッド監督の『グラン・トリノ』と、中国の路學長(ルー・シュエチャン)監督の『長大成人(原題)』です。『たそがれ~』を含め、これらは作られた時期も描かれている時代も違いますが、本作で描いていることと共通していると思います。
――まさに、ですね。90年代をロケで描くとなると、場所探しが難しかったでしょう。日本も中国もスクラップ&ビルドが大好きな国ですから、よくあの雰囲気のある工場を見つけましたね。
ガオ監督:はい、最高の場所を見つけたことはラッキーでした。吉林省に実際にある古い工場で、ほとんどのロケをその工場の敷地内で撮ることができたんです。稼働はしてない工場なんですが、昔の形のまま残っているので、ロケ地としては最高ですね。まるで映画村のような(笑)。ただし、稼働してない期間が長い場所はほぼ廃墟です。幸い、この工場はとても大きく、段階的に操業を止めたので、安全な建物もたくさんあったことで、撮影をうまく回すことができました。あるときは、撮りたい場所に10数年分のほこりが積もってたりしたので、「今、操業停止したばかり」という状態に戻すのが大変でしたけど(笑)。
――あるシーンでは高所の撮影がありましたよね。そこを含め、危険な場所での撮影は、初長編監督としてはプレッシャーだったのでは?
ガオ監督:あのシーンは、まずは登って何回もテストし、徐々に調整していきました。安全確保は第一です。でも、中国の映画演劇業界には、「役は金(きん)よりも大きい」ということわざがありまして。命を差し出して、とまで言わないけれども、その役を演じるためには自分の犠牲も払うのは構わない、っていう意味です。だから、彼らは演じる時はもう怖がってませんでしたし、私たちも彼らのために危険を取り除きまくりました。

――危険といえば火薬も。シュエビンの手製銃は最後まで大活躍でしたね。
ガオ監督:中国では子どもでも爆竹に慣れてますから(笑)。また、日本でもそうかもしれないのですが、現場での銃撃戦の音は、おもちゃのピストルみたいな音しか出ませんよね。役者さんたちは、非常に厳しいあの顔付きでほんとに真面目にシーンを演じてくれてるわけですけれども、音が何せおもちゃみたいなのしか出ないので、苦心したと思います。特にシュエビンがキメる最後の一発。私としてはシュエビンにもう涙を流してやってほしかったんですが、銃声はしない。それで、受ける側の役者さんは、音がないから「ピュー」って言ったんですよ。それで、もうそこの雰囲気が一挙に崩れちゃいました(笑)。それでもシュエビン役のズー・フォンは続けて演技をしてくれたので、役者さんはすごいなと思いましたね。
インタビュー/構成:よしひろまさみち(日本映画ペンクラブ)