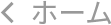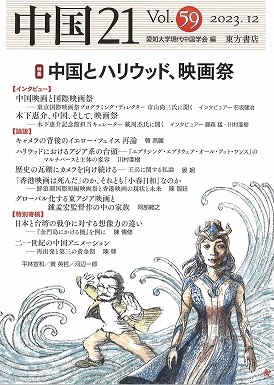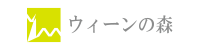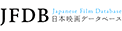安藤桃子監督、東京国際映画祭ナビゲーターへの挑戦 “角度をつける”ことの大切さを説く

安藤桃子監督 撮影:間庭裕基
第36回東京国際映画祭が、10月23日~11月1日に開催される。これまで俳優、女優が「アンバサダー」という形で同映画祭を盛り上げてきたが、今年はひとつの変革が訪れた。「アンバサダー」という名称を改めて「ナビゲーター」というポジションを設けることになったのだ。
白羽の矢が立ったのは、映画監督の安藤桃子だ。
1982年、東京都生まれの安藤。2010年に『カケラ』で監督・脚本デビューを果たし、14年には、自ら書き下ろした長編小説『0.5ミリ』を映画化。同作で報知映画賞作品賞、毎日映画コンクール脚本賞、上海国際映画祭最優秀監督賞などを受賞し、国内外で高い評価を獲得した。なお、『0.5ミリ』の撮影を機に高知県に移住。高知で映画館の代表も務め、自身で映画祭も企画するなど様々な形で映画にコミットし続けている。
映画祭をより楽しんでもらうための案内人――安藤は、そんな位置づけの「ナビゲーター」への就任について、どのように考えているのだろうか。その胸の内を明かしてもらった。
●世界中から“今”を描いた作品が集う「“私たちはどこに向かいたいのか”ということを感じとりたい」
――まずは、安藤監督と「東京国際映画祭」のこれまでの関わりについて教えてください。
映画祭が始まった頃、父(奥田瑛二)や周囲の大人たちが「東京国際映画祭」について話していたことを、今でも憶えています。映画人から聞く「東京国際映画祭」というものは、どうしても意識に入ってくるものです。自分の生まれ育った場所で開催されている映画祭でもありますし、自作を最初にお招きいただいた時は本当に嬉しくて、感慨深いものがありました。
――実際に映画祭に参加されてみていかがでしたか?
学生時代、父の初監督作『少女 an adolescent』が世界の映画祭に招待されたことで、通訳として世界中を巡った経験があります。大きな映画祭から小さな映画祭まで――映画祭巡礼の旅のような感じでした(笑)。その時に映画祭とはなんなのかということを教えてもらったような気がしていて。「映画」という言葉を辞書で調べると「総合芸術」と書いてあります。映画祭は、大きな予算の作品、低予算の自主映画、そしてありとあらゆる言語の作品に関わる人々が、同じレッドカーペットを歩きます。そしてコンペティションの場合は、分け隔てなく“映画愛”に基づいて審査される。それが衝撃的でしたし、やはり映画は“世界の共通言語”なのだと思いました。
そうやって世界の映画祭を巡り、映画を愛する人々と交流させていただいたことを踏まえて、「東京国際映画祭」というものを見ていました。今回改めて思いましたが、東京という日本の象徴的な場所に向けて、世界中から“今”を描いた作品が集ってきます。言い方を変えれば、そこには時代の方向性があるということです。
日本の、世界のこれから向かう先、そしてどこに向かっていきたいかということを、映画を見ながらたくさん気付くことができる。映画は、ひとつの作品を大勢の人々と一緒に体感するものです。観客それぞれが感じたことの集合体が、方向性を作っていくと思います。今回、たくさんの方に足を運んでもらい、国際交流を深めながら「私たちはどこに向かいたいのか」ということを感じとっていきたいです。
●ナビゲーターとしての役割 高知の“虹”に紐づけて考えたことも
――これまでの「アンバサダー」から名称を変更し「ナビゲーター」という立ち位置での就任となりました。まずは依頼を受けた際の率直な感想、自身で考えている「役割」について教えてください。
名称の変更については、めちゃくちゃ意識しますよね(笑)。運転をしている時、まずはナビにゴールを設定しますよね。「日本の中でナビゲーションをする」とは、どういう意味があるのかなと考えました。例えば「茶道」「華道」「武道」など、私たち日本人は「道」というものを見出してきました。そして、その「道」同士というのは、競い合って勝敗を決するというものではありません。その「道」を歩む者として、その「道」がどういうものなのか、何処へ繋がっていくのかということを重んじてきました。
今回「ナビゲーター」というポジションが生まれたということは、映画祭全体として「日本の映画道がどこへ繋がっていくのか」ということでもあり、国際映画祭としては「世界がどこへと繋がっていくのか」という方向性を示すことにもなります。コロナがようやく収束の兆しを見せたことで、世界中から“リアル”に人々が集まってくる。日本を代表する映画祭として、どういう心持ちで皆さんをお迎えすることができるのかということも考えています。
もう一つ考えていたのは、ここ最近の撮影の際には、多様性という言葉が出てくることがあります。(移住先の)高知県は、虹が頻繁に見えるんです。その光景を見て、山田洋次監督の「虹をつかむ男」を思い出すこともありました。そして、虹はグラデーションで構築されていて、いわゆる色の境界というものがないんですよね。それがさまざまな課題への答えのような気がしていました。全てが異なる色であっても、溶け合って、未来へと続くひとつの道へと繋がっていく。日本のカラーや、世界中から集まってくるカラーが、心を表現する映画というメディアを通じて、東京で織り成される。そうなっていったらいいなと思います。
今回は、小津安二郎生誕120年を記念した特集上映も行われますよね。“日本映画の父”でもある監督の作品が映画祭で上映されることにも意義があると思います。小津映画は、とても優しいんです。低く構えられたカメラで表現された映像は、日本人らしい“視線”ですし、父と娘が象徴的に描かれる一方で、その背景には戦争というものがある。色々な人の痛みや悲しみが描かれていますが、全体として温かく、見る者を包み込んでくれる。調和を大切にする私たち日本人の歩み方、人間性の象徴でもあるのかなと考えています。
●「映画で“変わる”」という体験について “角度をつける”ということが重要
――映画祭は「映画を鑑賞する場」だけでなく「交流する場」でもあります。今仰っていただいたように、今回は多数のゲストが来日予定です。安藤監督は、どなたとの交流を期待していますか?
まずは、審査委員長(ヴィム・ヴェンダース監督)! 山田洋次監督もお話するタイミングもありますし、いわゆる“レジェンド”がわんさかいらっしゃる印象なので、存分に交流ができたら光栄です。映画祭にいらっしゃる皆さんは“全体”を見ていかれると思っています。映画界、これからの世の中、社会の状況、映画人としてこれからどこに向かいたいのか――。(ナビゲーター就任発表時の)コメントにも書かせていただいた「映画祭は世界の羅針盤だ」という言葉に紐づきますが、指針や方向性というものは、ゲストの方々からも自然と生まれてくるんじゃないかなと思っています。
――コメントの中には「映画は世界を変えられる」「映画で世界が変わる」という記述もありました。「映画で“変わる”」という体験、かつてどのようなことがありましたか?
映画で“変わる”――それは常々です。良し悪しは関係なく、どんな作品を観たとしても“変わる”んです。アートというものは、アート自体にあるわけではなく、見ている人の心の中にあります。映画も誰も見ていない状況で上映されていても、それはただのモノでしかない。届く先がないと成立しない。私たちひとりひとりの中に作品があり、その人が何を受け取り、どう響いたのかが重要です。どんなものを見たとしても、心の中では“反応”が生まれます。それ自体が経験と体験として“変化”をもたらしていきますから。例えば、自分の“今”に響く作品に出合うと、10年経とうが、20年経とうが、ずっと響き続けます。そんな作品は、自分の人生とともにループし続けていく。映画祭は、そういった作品との出合いがたくさんある場所です。
先程示した「羅針盤」について。東西南北のイメージが強いと思いますが、どちらかというと“角度をつける”ということが重要なのだと思います。子どもたちに参加してもらうワークショップをやっていると「自分の理想に近づけていない」「自分は変われていない」というようなことを聞くんです。でも、1ミリでも、もしくは0.000001ミリだとしても“角度”が上がれば、時間が経つにつれ、その“角度”というものは、10年後、20年後に大きな“変化”になっているはず。映画は、ちょっとした視点や捉え方の“変化”が大切です。些細なことでも、そのタイミングで明確に気づけていなかったことでも、そこで生じた“角度”というものはめちゃくちゃ大きいもの。そういったものが誰しもに芽生えていき、またその人が他者と関わり、互いに影響を及ぼし合っていく。だからこそ、映画は世界を変えられると思っています。心に作用する文化というものは、世界を変えるきっかけになる。
●東京国際映画祭を経て、人々の記憶・印象に“残っていってほしい”ものは?
――「鑑賞して“損があるか”“損がないか”」という選び方があると思いますが、それは違うのではないかと常々考えていました。安藤監督が仰るように、質の良し悪しは関係なく、鑑賞することで確かに“変化”というものは生じますよね。
そう! “変わる”んです! 余談になってしまいますが、学生時代に見た実験映画のことを思い出しました。2時間ずっと同じ窓を映し続けていて、何かが起きるのかと思いきや、結局何も起きない。ロシアのある作品では、息子が病気の母を背負って、山中をただただ歩く……何かドラマが生じるのかなと考えていたら、その描写で終わってしまいました(笑)。当時は「なんだかよくわからないなぁ」という感覚でしたが、今この瞬間にも、その映像というものはしっかりと思い浮かべることができるんですよね。行ったこともないのに、その山が、風や木々が、心の記憶に刻まれているんですから。
地球に立っている限りは、皆が繋がっている――高知の木を見ていると、そう思うんです。先日、高知で樹齢3000年の大杉を見て、考えたことがあります。木々はネットワークで繋がっていて、隣り合う木々と根っこで情報交換をしている。そこには虫や微生物も介在している。“地球の裏側”は全部が繋がっているんだと。私たち人間もそれらと一体化して存在している生き物ですし、やはり地に足が触れている限りは、全ての物事と繋がっているんです。
感動すると“震える”と表現しますよね。その振動が伝わることで、世界中が震えていくわけです。感動は共鳴し合うもの。だからこそ、東京国際映画祭という場所から、世界への愛を響かせていけるのではないかと考えています。
――では、東京国際映画祭が終わった後、人々の記憶・印象にどのようなことが“残っていってほしい”でしょうか?
自分のエッセイのタイトルではあるのですが「ぜんぶ 愛。」に尽きると思います。どんなテイストの作品だったとしても、そこには“愛”が存在していると思います。映画は、物語の過程でどんなことがあったとしても、最後に向かう場所が大きなポイントとなっていきます。苦しい事や辛い事があったとしても、結果的に“どこにいるのか”が大切なこと。今回の映画祭で経験したことが、映写機の灯りのように、みなさんの行く先を照らしていけたらいいなと考えています。
新着ニュース